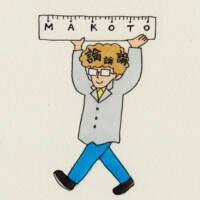命さえつないでもらえれば結構と 道弘めに一身を捧げて 中川よし(上) – おたすけにいきた女性
2024・7/10号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
おたすけに掛かると、二昼夜かけて丹波とおぢばを徒歩で往復し、幾度となく寒中の水行を重ねたよし。不思議なご守護が続出するなか、初めは冷ややかだった人々も、わが身を顧みず奔走する「たすけのおよし」を慕うようになった
今回紹介するのは、中川よしです。明治2(1869)年、兵庫県多紀郡篠山町(現在の丹波篠山市)に住む明山謹七、うのの長女として誕生。明治20年、中川弥吉と結婚し、2男3女を授かります。教祖ひながたの話に感激して入信して以来、生涯おたすけに励み、東本大教会の初代会長に就任します。
教祖ひながたの話に感動して
明山家は青山藩の御用達商人として、蔵米払役をしていました。よしの両親は品と教養があり、躾や礼儀作法に厳格な人でした。
明治維新で藩が廃止されると、生計の道がなくなり、父・謹七はすっかり変わりました。商売や事業に失敗を重ね、道楽も激しくなり、わずかな間に財を失います。家屋敷を売り払って船井郡南大谷村へ移り、しばらくして同郡東本梅村赤熊へ移住しました。
よしは母・うのに苦労をかけまいと、着物一枚も欲しがらず、よく手伝いました。7歳のとき、うのが眼を患い、よしは手ぬぐいを絞るなどして夜通し看病しました。
13歳ごろから子守奉公に出ます。17歳から3年間、酢や醤油を醸造する家で奉公しますが、謹七は、よしや弟二人の給金を前借りし、縁を切って家を出ていきました。奉公先でのよしは、物を大切にし、その働きぶりも模範的でした。お盆と年の暮れに奉公先から頂く着物は母に届け、自身は母の着古しを身に着けました。
明治20年2月、よしは中川弥吉と結婚します。弥吉34歳、よし19歳でした。弥吉は酒を飲み、道楽をして財産を蕩尽しました。さらに、八坂峠の工事を請け負って損害を出し、家も田畑も人手に渡りました。
同23年、よしたちは、弥吉の姉夫妻が暮らす大阪へ移り、赤熊の特産物の木賊、椋葉を商いました。姉夫妻は、南大教会初代会長・松永好松に導かれ、すでに信仰していました。よしたちも姉夫妻に勧められて集談所へ行き、何度か参拝するうちに転機が訪れます。
ある日、教祖ひながたの話を聞いたよしは、感動して涙が止まらなくなりました。このときのことを、「初めて教祖のご履歴を伺って、世の中にはそれほど尊いお方もおありなさるのに、自分は数にも足らぬ勤めを行って、それに満足を抱いたり、不足を感じたりした自分の了見に愛想がつきた。ただもう私は、自分の身に立ち返って恥じ入るばかりで、打ち倒れて泣きました」と述懐しています。幼少期から苦労してきたよしの心に、世界たすけのために、どのような道も陽気に歩まれた、ひながたの話が深い感激を与えたのでしょう。
一人のおたすけに百里歩く
しばらくして、よしは不思議な経験をします。弥吉が、ある女性の家へ行って帰ってこなくなりました。よしがその家で立ち聞きしていると、弥吉が女性をだましていることが分かりました。「あんな夫は、盲目にでもならなければ家へ帰らないだろう」と思っていると、間もなく弥吉が風眼に罹って帰宅しました。よしは、驚くとともに申し訳なく思い、こうした夫と連れ添う自分こそ、よほどいんねんが深いと悟ります。神様に、夫の患いを自身に代わらせてください、と一心不乱にお願いすると、弥吉は全快し、よしが眼を患いました。よしは喜んでお礼を申し上げ、間もなく、よしの眼もご守護いただきました。
よしは、大阪でおたすけの第一歩を踏み出します。磨き砂売りの女性が、頭に瘡ができている子供を連れているのを見かけ、おたすけを申し出ると、3日のお願いでご守護いただきました。よしはおぢばへ帰り、お礼を申し上げました。
「活きるも、死ぬるのも、神様の思召次第である。明日にも神様のご催促があれば、この身体は、すぐに差し上げなければならないのであるから、今日ただいま、私は死んでしまったつもりになって、一身を神様に捧げ、この道を弘めることに従事しようと決心しました」と、当時の心境を述べています。
明治24年の暮れ、松永好松は丹波布教を決意し、弥吉たちに同道するよう説得します。好松は赤熊の日下部寅治郎宅に滞在し、病人を手引きしてもらって、おたすけに励みました。一方、よしたちは、家を借りて布教を始めます。しかし、よしは篠山出身のため、よそ者扱いされ、生活状態が低いことや弥吉の過去の行状もたたって悪評を受けました。歩いていると聞こえよがしに悪口を言われ、子供らも村中の子供にいじめられました。
よしは毎日布教に歩きますが、誰も話を聞いてくれません。なんとか神様にお働きいただきたいと考え、一人のおたすけに百里(400キロ)歩く心を定めました。にをいが掛かったら、お願いにおぢばへ参り、その人がたすかったら、お礼参りをするのです。赤熊からおぢばまでの約100キロの道のりを、よしは子供を背負い、眠る間もなく2日間で往復しました。

後年、よしが赤熊を訪れた際に随行した三戸部邸治郎は「男でさえも気味の悪いこんな山の中を、女の身でありながら、お子さんまで背負って、夜となく昼となく、西に東に、食うや食わずで、人だすけに歩いてくださった。どれだけご苦労であったことだろう」と思うと、涙が止まらなかったといいます。
水垢離をとって懸命に願い
よしは、おたすけに励みつつ、時々、大阪の南や髙安へ神様のお話を聞きに行きました。一度にたくさん聞いても覚えられないからと、ひと言ふた言教えを聞いたら、お礼を言って帰るのでした。一つ聞いては3カ月間や半年間実行し、継続できるようになったら、また聞きに伺いました。そうして全身全霊で教えに沿って生きようと努めたのです。
明治26年7月19日、よしは、おさづけの理を拝戴します。「私は何もいりません。どうぞ、今日頂きますおさづけを、朝から晩まで使わせてくださいませ。これが生涯の私のお願いでございます。毎日おさづけを取り次がせてくだされますなら、ご飯を頂けなくとも結構でございます」と、神様にお願いし、この約束を生涯貫きました。
次男・光之助が生まれるころ、よしは眠る間もないほど忙しくなり、神様に何度も出産の延期をお願いするうちに、予定日をかなり過ぎました。産気づいてから集談所の人が出産の手伝いに来ると、家には釜もなく、穴のあいた鍋が一つあるだけでした。人々は、よしがこれほどの道を通っているとは知らず、泣きながら家に戻り、釜、盥、柄杓、米や味噌などを持ち寄ったといいます。
よしは、晴れの日は傘の上でおしめを干し、雨の日は素肌に巻いて体温で乾かしながら、布教に歩きました。おたすけにかかると、水垢離をとって懸命に神様にお願いしました。このころは、お供えを説かず、ただただ誠の心になることを求めました。難しい病気の人のおたすけでも、たすかる前に本人か代理の人をおぢばへ導きました。自身は命さえつないでもらえれば結構と、食べ物、着る物もないなか、その合間に農家の手伝いや魚売りなどをして得たお金や物も、困窮している人に惜しげもなく与えたのでした。

よしの丹波布教は「踊ってつけた道」ともいわれます。この家の人をおたすけすると決めたら、何を言われても、どんな目に遭わされても、ニコニコと受けて帰り、翌日また行きました。そうして二、三度運ぶと道がつきました。信者宅では、神前で拝をするとすぐにおつとめを始め、「あんたも来なさい」「あんたも来なさい」と家中の人を踊らせました。農繁期は、昼休憩や夕方に帰宅した人と共に土間や庭先で勤めたといいます。
こうしてよしは、一人でも多くの人にたすかってもらいたい、たすかってくださりさえすればよいとの思いでおたすけに励み、「たすけのおよし」と呼ばれるようになります。 この後、おたすけの場を丹波から東京へ移します。次回は、東京へ赴いたよしが数々の試練を乗り越え、おたすけに生きる姿を見ていきたいと思います。
(つづく)
文・松山常教(天理教校本科実践課程講師)