第3回「心の皺を、話の理で伸ばしてやるのやで」- おことばに導かれて
2025・9/10号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
第19期読者モニターアンケート企画
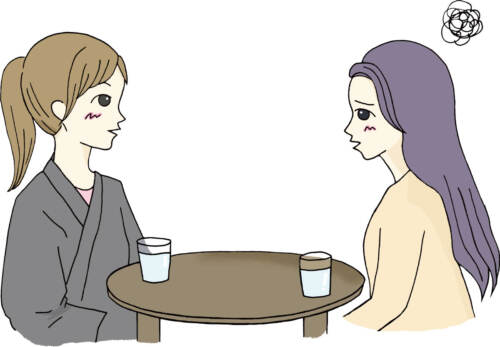
『稿本天理教教祖伝』や同『逸話篇』に収められている教祖のお言葉を題材に、教えの大切さに気づいた体験などについて、読者モニターが“お言葉に導かれた”と感じたエピソードを語るコーナー「おことばに導かれて」。第3回は「心の皺を、話の理で伸ばしてやるのやで」(『逸話篇』45「心の皺を」)。教祖140年祭活動のさなか、ようぼくがさらに強い意識をもって布教活動を行う「全教会布教推進月間」が始まった。ようぼくお互いは、残り5カ月となった三年千日の期間、自らが教えを心に治めるとともに、一人でも多くの人にお話を取り次げるようにをいがけに励むことが欠かせない。今回は「心の皺を、話の理で伸ばしてやるのやで」とのお言葉にまつわるエピソードを読者モニターに寄せてもらった。
苦境にある人を救った出会い
田岡利依さん
47歳・東三分教会ようぼく・天理市
先日、認定心理士の勉強会に参加したときのことです。
班でプログラムに取り組むなか、班員の一人が「実は天理教の方にたすけられ、今日ここに来ることができた」と話し始めたので驚きました。聞くと、仕事が原因で人間不信になっていたところ、戸別訪問で自宅を訪ねてきた天理教の教会長の奥さんと親しくなり、話を聞いてもらううちに心が救われたと言います。その後、教えを聞き、現在は別席運び中で、将来、自分がたすかったことを人に伝えたいと話していました。この話を聞き、とてもうれしい気持ちになりました。
この出来事から、ようぼくがにをいがけに歩けば、教祖が苦境にある人々に温かい手を差し伸べてくださるのだと感じました。私も日々勇んで通り、教祖にお使いいただけるようぼくになりたいと思います。
講師の体験談に感銘を受け
小長谷啓太さん
49歳・華越一分教会ようぼく・名古屋市
今年3月、大教会で開催された「布教推進講習会」に参加しました。講師自らの体験をもとにした数々の不思議なご守護や布教における心構えについて話を聞かせていただき、深く感銘を受けました。
これまで、妻がお道の話を子供に分かりやすく伝える姿を見ては、「自分も見習わなくては」と反省することが少なくありませんでした。今回の講習会を機に、自ら積極的にお道の教えを子供たちに話すことを心がけています。
昨年の「全教会布教推進月間」では、初めてお会いした布教所長さんと共にリーフレット配りに取り組み、新鮮な気持ちでつとめさせていただくことができました。今年も自分にできる実践を続け、講習会で頂いた“勇みの種”を胸に、成人した姿を目指していきます。
原典に親しんで心が前向きに
髙橋ひろみさん
55歳・船三咲分教会教人・天理市
4月、微熱や血圧低下といった身上のお手入れを頂き、自宅療養をすることになりました。「三年千日最後の年を、教祖にお喜びいただける一年に」と勇んでいただけに、落ち込む日が続きました。
そんななか、次第に心が落ち着いてきたので「家でできることをしよう」と、自宅で朝夕のおつとめを勤めることに。それまで疎かにしていた原典や『天理教教典』の拝読も始めました。
すると、さまざまな発見がありました。「おふでさき」には心励まされるお歌がたくさんありました。原典や『天理教教典』第三章「元の理」には、身上のときの心の治め方や十全のご守護の有り難さが示されており、「かしもの・かりもの」の理の尊さをあらためて学びました。
体調はまだ十分ではありませんが、少しずつ気持ちが前向きになってきました。今後も「かりもの」の体を大切に使わせていただき、いまできる実践に努めたいと思います。
叔母の言葉を心の支えとして
大谷吉輝さん
44歳・芦住分教会教人・佐賀県白石町
令和元年と3年、豪雨によって河川が氾濫し、その両方で叔母の自宅が浸水被害に見舞われました。叔母はパーキンソン病を患いながらもよく働き、信仰も熱心でした。災害が起こる前、私は叔母の家によく立ち寄り、悩みを相談していました。叔母は「何事も言葉一つで相手の気持ちは変わるから、常に笑顔で、感謝の心で接していればなんとかなる」と諭してくれました。その言葉に、いつも救われていました。
水害をきっかけに叔母は遠方へ引っ越しました。災害で多くのものを失いましたが、叔母が笑顔で通る姿は、いまも私の心の支えになっています。
以前のように頻繁に会うことはできなくなりましたが、叔母が伝えてくれた言葉を心の支えとして、感謝の気持ちで毎日を過ごしています。
おたすけ人としての心構え
松村 純さん
51歳・博門分教会長・福岡県北九州市
以前、支部の「ようぼく成人講座」を受講する機会がありました。
質疑応答の時間、一人の参加者が「知り合いが重い病で苦しんでいます。力になるには、どうしたらいいでしょうか」と質問しました。講師の答えは「一緒に泣いてあげてください」。そのひと言に、おたすけ人としての心構えが凝縮されていると感じました。
心が倒れそうなときは、寄り添う姿勢が大切だと切に感じます。私も息子が中学時代に身上を頂いて入退院を繰り返したときは、つらい日々を過ごしました。そんなとき、ある先生からかけてもらった「つらい思いをした分、人の痛みが分かる。いつか同じつらさを抱える人をたすけてください」との言葉に心救われました。
いまもこの言葉が心の支えになっています。意識しているのは“心のアンテナ”を張ること。困った人がいればすぐに手を差し伸べられるよう、自分自身に言い聞かせる毎日を送っています。
ココロ整う My Routine
寝る前のあいさつ
山根博子さん
71歳・愛松分教会教人・兵庫県明石市
就寝前、夫に一日の感謝を伝えています。会社勤めをしていたころ、夫は海外・国内への出張や単身赴任が多く、家庭で一緒に過ごす時間が限られていました。まさに激務の日々だったと思います。
そんな夫も定年退職を迎え、いまは穏やかな日常を送っています。厳しい仕事をやり抜いた後も元気でいてくれることは、本当に有り難い限りです。そうした思いから、毎晩一日を終えるときに「お父さん、今日もありがとうございました」と伝えると、夫も「お母さんもありがとう」と返してくれます。
そのやりとりで私の心が安らぎ、体の調子も整い、ぐっすり眠れています。これからも、このささやかなルーティンを続けながら、日々を大切に過ごしていきたいと願っています。
この一行をあの人に
7月16日号から8月13日号までの紙面の中から、読者モニターが、「あの人に読んでほしい」と思ったオススメ記事を紹介する。
“あの人”をおぢばへ 「こどもおぢばがえり」引率者の声
(8月13日号8面)
子供が幼いころ、所属教会のおぢば帰り団参を引率したことを思い出しました。子供たちを楽しませる中で、私自身が教友とのつながりを強めることができ、いい思い出になりました。引率を引き受けるかどうか迷っている人に読んでほしいです。(40代女性)
子供たちの「楽しかった」との声を聞き、満足して終えた「こどもおぢばがえり」。来年もたくさんの人をお連れできるように、子供の友達を早速誘い始めた。声かけを頑張る人の勇みの種として、この記事が届いてほしいと感じた。(40代男性)







