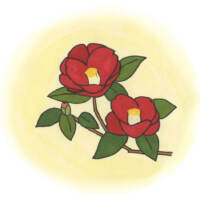昔も今も変わらぬ「ぬくもり」- 視点
2025・12/17号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
教祖が現身をもって過ごされていた当時、人々が教祖に対して抱いた印象を、『稿本天理教教祖伝』では、次のように記している。
教祖にお目に掛る迄は、あれも尋ね、これも伺おうと思うて心積りしていた人々も、さてお目に掛ってみると、一言も承らないうちに、一切の疑問も不平も皆跡形もなく解け去り、ただ限りない喜びと明るい感激が胸に溢れ、言い尽せぬ安らかさに浸った。
第八章「親心」
ここで表現されているような感覚や感情は、何も昔に限った話ではない。いまも私たちは、教祖の御前に出させていただくと、大きな安らぎに包まれ、温かな気持ちが胸に込み上げてくる。難しい理屈は抜きにして、この胸の温かさこそが、教祖がご存命でお働きくださっている証拠ではないだろうか。
教祖の孫に梶本ひさという方がいる。明治13年ごろから、始終、教祖のお側に仕え、そのお世話をされた方である。明治20年に現身をおかくしになられるまでの5、6年の間、教祖のご様子を一番間近で見ておられたことになるだろう。
その晩年ごろのことである。「教祖という方は、どんな方だったのですか」と尋ねる人があった。それに対して、ひと言、「教祖は湯たんぽみたいやった」と答えたという。
『みちのだい』191号
「湯たんぽ」という言葉の中に、教祖の、まったりと心地よく、温かい、親のぬくもりが、よく表れている。
湯たんぽの中身であるお湯は、水と火のお恵みである。「火と水とが一の神」と教えられるところから思案すると、まさに教祖のお心は親神様のお心で、世界一れつを常に温かいお心でお守りくだされている。
そして、この教祖のぬくもりこそが、おぢばの温かさの芯のところ、お道を信仰する者にとっての活力の源なのではないかと思う。
教祖年祭まで、あとわずか。最後までしっかりとつとめきり、年祭当日、おぢばに帰り、教祖にお目通りさせていただこう。
(山澤)