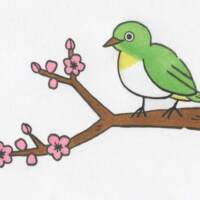「陽気ぐらし文化」考 – 視点
2025・2/19号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
一昨年、天理大学杣之内キャンパスに佇む天理大学附属天理図書館が、国の登録有形文化財に登録された。昭和5年竣工の同館は、当時のミネソタ州立大学の図書館の設計図を参考に、京都帝都大学助教授の坂静雄氏と、学校建築を手がけた島田良馨氏が設計した西欧風の建物だ。格式高い文化財であるとともに、所蔵図書が質量ともに高評価を得ており、「AERA MOOK進学『大学ランキング2021』」(朝日新聞出版)の大学図書館ランキングでは総合1位を獲得した。
文化的価値があるとされるコトやモノには、必ずそれに携わる人がいて、それを現代まで伝えてきた人々がいる。一部の人たちによる新しい行動が起因となる「創生期」。早い段階で広範囲に成果が周知される「成長期」。そして、その行動と成果が拡大し、新しい行動パターンとして社会に根づく「拡大期」を経て、最終的に文化として定着するといわれている。
天理図書館でいえば、創設者である中山正善・二代真柱様のビジョンに沿った設計者や施工者の創意工夫、そして所蔵資料の蒐集に長年尽力された方々がいたがゆえに、文化的価値がある。
また、スポーツも文化の一つである。天理スポーツも、二代真柱様が天理高校と天理大学に柔道とラグビーを導入されたことが始まりとされる。多くのオリンピアンが輩出した天理柔道は、社会で高く評価され、「しっかり組んで一本を取る」というスタイルも柔道界で定着している。昨年10月には、天理大学柔道部が日本柔道連盟からの要請を受け、中高の柔道部の協力のもと、戦時下で強化のままならないウクライナから選手や指導者ら二十数人を受け入れた。天理に柔道の文化が根づいている一つの証左だろう。
翻って、私たちの信仰のうえでは、道が広がり、共に歩む人が増えていくことで、陽気ぐらしの生き方が社会の文化となり、その真価を発揮する。それは、私たちが教えを実践することによって醸し出す「にをい」が外へ向かうとき、人々との触れ合いの中で発揮されるだろう。そして、その元には、常に教祖がおられ、おぢばがある。教祖がおられるから、お道は文化として熟成し、私たちようぼくが担い手となって伸び広がる。
「陽気ぐらし文化」の拡大期、定着期を明るく思い描き、教祖140年祭へ向かう最後の年を、一歩ずつ着実に歩みを進めたい。
(永尾)