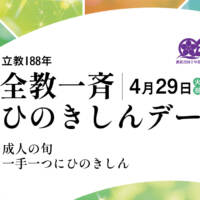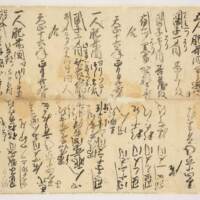たすける相手を見据えて – 視点
2025・4/2号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
年明け、政府の地震調査委員会はマグニチュード8~9が想定される南海トラフ地震の30年以内の発生確率を「80%程度」に引き上げた。調査委員会の委員長を務める平田直・東京大学名誉教授は「いつ起きてもおかしくない数字」として警鐘を鳴らし、緊急時への備えを呼びかけた。
この値は、ある予測計算モデルを使って過去の大規模地震の発生間隔や規模などから割り出したもので、2013年に公表されて以降、上昇を続けている。正直、心中穏やかではいられない。いつ発生するとも分からない自然災害に対し、個人にできる防災には限りがある。とはいえ、いざというときにものをいうのは平時の意識と行動だろう。
近ごろ、興味深い施策を知った。総務省は2月、南海トラフ地震による被害が甚大とされる太平洋沿岸の10県を支援する自治体を、「即時応援県」として事前に指定することを決定した。”応援県”は主に日本海側や北関東から選ばれ、なかでも被害が大きいとされる5県には複数の県や市が支援する態勢が取られている。ペアとなった自治体は、合同での災害訓練や被災想定地域の視察、応援に向かう交通ルートの確認などを行うほか、有用なノウハウを持つ職員のリストを交換し、円滑な運用を目指す。また有事には、災害対応に慣れた職員を直ちに派遣し、避難所の運営や罹災証明書の発行などを支える。この4月から運用が始まるという。
従来行われていた「対口支援」は、地震発生後、国が被災側と応援の自治体を1対1で割り当てるというものだ。あらかじめペアとなる相手が分かっていれば具体的な対策も立てやすい。こうした取り組みは大いに進められるべきだろう。
ところで、たすける相手を明確にするという点は、信仰活動にも一つの示唆を与えるものだと思う。家族や友人、同僚など「自分はこの人に教えを伝えよう」という視点を持つことは、普段からたすけ心を養うことに通じる。また、「どうすれば理解してもらえるか」という苦心は己の成人にもつながるはずだ。
地震などの天災は、成人の鈍い人間に対する親神様の残念・立腹の表れであり、子供可愛いゆえのお仕込みであると教えられる。思召に沿う、教えに根ざした生き方に、当たり前の日々をご守護いただく元がある。身近な”この人”に教えを伝えようとする不断の努力がいま、一層求められている。
(春野)