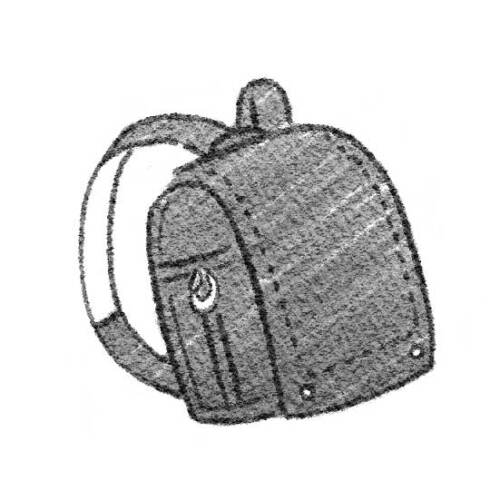虫嫌いの増加が与える影響 – 陽のあたる方へ 11
2025・4/9号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
私どもが開いている「こども食堂」では、農家さんの支援を頂いて農園を運営しています。始めた動機は、自分で育てた野菜なら野菜嫌いな子供たちも食べるのではないか、また農作業を体験することで農家に感謝を抱き、食べ残しが減るのではないかと考えたからでした。実際に運営してみると、子供たちの知られざる実情が見えてきます。その一つが、虫嫌いの子が多いということです。
ほとんど無農薬で野菜を栽培している農園には、虫がたくさんいます。ある小学生の男の子は大の虫嫌いで、野菜の世話や収穫のときは、いつも「怖い、怖い」と大騒ぎ。「収穫は楽しいけれど、虫が怖い」と、途中でやめてしまうこともありました。ところがある日を境に、彼はすっかり変わりました。お母さんに聞くと、家の玄関を出たところで美しい虹色の虫をふと発見したそうで、その姿に魅了されて以来、絵をよく描くほど虫が好きになりました。
現代人の虫嫌いは、自然に触れる機会の減少によるものとされています。好き嫌いは個人の自由、嫌いなら避けて暮らせばよさそうなものです。しかし生物学者らは、虫嫌いの増加が生物多様性の保全が進まない要因の一つだと警鐘を鳴らしています。
2017年秋、昆虫が27年間で75%以上減少したとの研究がドイツで発表され、大きな衝撃を与えました。昆虫は、植物の花粉媒介者や動物などの食物資源であるとともに、有機物の分解や有害な生物のバイオコントロール、水域の浄化、肥沃な土壌の維持を行うなど、生態系において重要な役割を果たしています。昆虫が減少し生態系の営みが損なわれることは、環境に直接影響を与えるだけでなく、人間にも大きな影響を及ぼすのです。
「おふでさき」に「たん/\となに事にてもこのよふわ 神のからだやしやんしてみよ」(三号40、135)と、この世のすべては親神様が創造されたものであり、「神のからだ」とお教えいただきます。私たち信仰者は、借りものである体を貸主である親神様の思召に適うように使うことはもちろんですが、親神様の懐で共に生きる存在の重要性を、子供たちに教えていくことも大切ではないでしょうか。