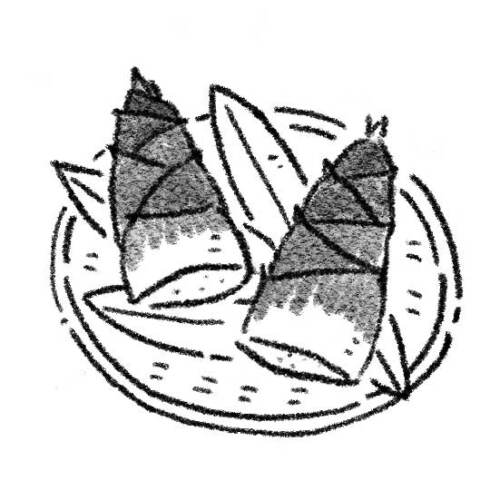理科系人材の可能性 – 陽のあたる方へ 最終回
2025・5/14号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
私が関わる蓄電池の技術開発において、いま大きな問題となっているのが「バッテリー人材」の大幅な不足です。バッテリー人材とは、電池自動車などに使われる蓄電池の研究開発や製造に関わる人のことです。電池関連産業が多く集まる関西圏では、今後5年間に約1万人の雇用が見込まれる一方で、その人材確保は深刻な状況にあります。
バッテリー人材にはこの先、新たなイノベーション(発明)を通じて人類最大の課題の一つである「地球温暖化」問題の解決を目指し、大学や企業で持続可能な世界である脱炭素社会を実現するための技術を生み出すことが求められます。蓄電池の市場規模(世界)は、2019年は約5兆円でしたが、30年には約40兆円、50年には約100兆円に拡大すると予測されています(経産省試算)。世界で初めてリチウムイオン電池の製品化に成功し、電池の研究開発をリードしてきた日本にとっても、重要な産業の一つです。
ところが、昨今の日本ではバッテリー人材も含めて、理科系人材が減少。子供たちの理科離れが深刻な課題となっており、工業立国である日本の産業を支えてきた人材の育成・確保がままならない状況に陥りつつあります。
「令和4年度全国学力・学習状況調査 報告書・調査結果資料」(文部科学省)によると、「理科の勉強は好きですか」という質問に対して、小学生の約50%、中学生の約32%が「はい」と回答した一方で、「将来、理科や科学技術に関係する職業に就きたいと思いますか」に対して「はい」と答えたのは、小学生で約13%、中学生では約8%と、仕事として魅力を感じないという結果でした。
教祖は「働くというのは、はたはたの者を楽にするから、はたらくと言うのや」(『稿本天理教教祖伝逸話篇』197「働く手は」)とお教えくださいました。
私自身、このお言葉を胸に、今後も蓄電池の開発に関わる者としての「働き」を果たしていくとともに、「こども食堂」などの活動を通じて子供たちに理科を学ぶことの魅力、そして、その先には社会や世界の人々を救う大きな可能性があることを伝えていきたいと思います。
乾 直樹(京都大学大学院特定教授・大阪分教会正純布教所長後継者)