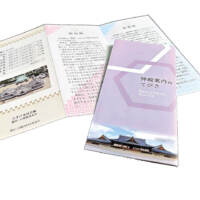「無用の用」は「大用」- 視点
2025・7/16号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
来る7月26日から奈良国立博物館において「奈良国立博物館開館130年・天理大学創立100周年記念特別展『世界探検の旅――美と驚異の遺産』」(奈良国立博物館・天理参考館合同)が開催される。会期が「こどもおぢばがえり」とも重なり、中学生以下は入場無料ということもあるので、多数のご利用を期待したい。
天理参考館は中山正善・二代真柱様が、海外布教師の生活文化理解の扶けとして「海外事情参考品室」を昭和5年に設けられたことに始まる。やがてそれは天理参考館へと成長し、創始者の意思を継承する大勢の人々の協賛を得て充実発展の途を辿り、文化的な立場から、世界布教に役立ち、陽気ぐらしに寄与することを目的として活動を続けてきた。
そうしたなか、あるとき(昭和40年ごろ)、参考館における天理教と考古学との関係について尋ねられた二代真柱様は「一言で言えば、無関係という関係でしょう。だがそれをどう役立てるかということについては今後我々が考えなけりゃならん」(天理図書館報『ビブリア』30号)と、参考館の将来について示唆されている。
「無用の用」という言葉がある。役にたたない実用性のないようにみえるものに、実は真の有益な働きがあるという譬えで荘子の言葉に由来する。「無用の用」の最たるものは「教養」というものではないかと筆者は考える。すぐに役立つものではないが、やがて、その者にとってはかけがえのない力となるものである。
いまから50年余り以前に発刊された『天理参考館四十年史』にはすでに、「将来への展望」と題した頁の中に次のような記述を見いだすことができる。
「お道の教えを伝える人々への教養は、やがては世界人類への内容豊かなしかも現実に即したコミュニケーションとなって発揚・展開されるべきであり、参考館の使命は、世間の評価は暫く別として、天理教自身の立場から見ても重く、その活用は真剣に営まれなければならない」と。
「無用の用」は「大用」でもある。
(橋本)