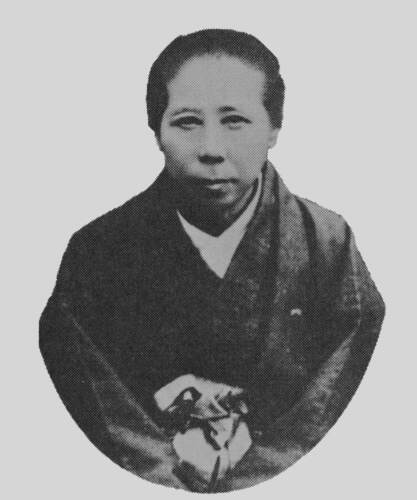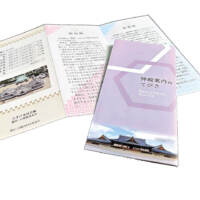神様に立てた誓いを守り 不屈の信仰でおたすけへ 加藤きん(上)- おたすけに生きた女性
2025・7/16号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
幼少期、大商家の箱入り娘として育ったきんは、多くの労働者と暮らすうち、見違えるほど芯の強い女性に生まれかわったという。直情径行の雇人たちからは「姉御」と呼び慕われていた
今回紹介するのは、加藤きんです。慶応元(1865)年、愛知県丹羽郡犬山町西古券に住む加藤甚三郎の長女として誕生しました。佐野弥市郎と結婚し、2女を授かります。娘の身上をきっかけに入信し、夫の仕事の都合で渡った台湾でおたすけに励み、嘉義東門教会初代会長に就任しました。
娘の身上から日参を勧められ
生家は尾張犬山城主の御金融御用達を代々勤めた大きな商家で、きんはその娘として育ち、先方に請われて嫁ぎました。

夫の弥市郎は徳島県名東郡佐野塚村に生まれ、大倉組に勤務し、のちに佐野組をつくり、請負工事を担いました。家の跡取りでしたが、鉄道敷設やトンネル掘削、鉱山採掘を請け負い、国内を転々としました。結婚当初、弥市郎はきんを可愛がりますが、やがてすき間風が吹き始めます。きんも加藤家の相続人で、自身の両親を抱えていました。そのため転居の多い夫に同行せず犬山に残り、長女・まさを出産しますが、弥市郎はいつのころからか愛人をつくっていました。初め、きんは憤りますが、自分に代わって夫の世話をする人と割り切るのでした。
明治29(1896)年、弥市郎は常磐線の鉄道敷設工事を請け負います。きんは労働者たちの食事を賄うよう夫に催促され、両親を犬山に残して福島県久之浜へ移りました。ところが、次女・ひさが6歳ごろから歩行困難になり、8歳になる年に背中の痛みを訴えます。ひさは脊椎カリエスと診断され、やがて下半身が麻痺しました。きんは一生重荷を背負う娘を思い、悲嘆に暮れました。
当時、山名の道は北関東に及び、福島県でも広く知られていました。きんは、飯場で働く女性らが、ひさの病気について、「天理さんにお願いすれば治るのに」と口にしているのを聞きつけ、明治33年7月、藁にも縋る思いで天理教久之浜出張所を訪ねます。所長の藤沢林太郎に、どんなことでもするので治るように祈ってほしいと泣いて訴えると、日参を勧められました。きんは、ひさを背負って毎日参拝し、おさづけを取り次いでもらうと、ひさの下半身に血の気が差し始め、やがて手に縋りながら歩けるようになりました。きんは毎日が感激の連続でした。
神様との約束を果たすため
弥市郎の工事が終わると、八茎鉱山へ転居しました。きんの心も信仰から次第に遠のき、ひさの弾む心も消えたころ、再びひさの背中が痛みだします。東京の大学病院で検査を受けますが、治癒の見込みはないと言われ、ひさは泣く泣く退院しました。一縷の望みも断ち切られたきんは、毎日、娘の足を撫でさすりながら泣きました。
そんなある日、ひさがもう一度教会へ行きたいと訴えます。きんは人間思案に終始していたことに気づき、横っ面を張られたような衝撃を受けました。
それから、11歳の娘を背中に結びつけ、八茎から久之浜まで約16キロの道のりを、5、6時間かけて参拝しました。労働者の夕食の片付けが終わる夕刻に出発し、一歩間違えば谷底へ転落しそうな山道を、提灯のあかりを頼りに歩きました。
所長の藤沢は、ほこりの心をさんげし、天理に適う心になるよう促し、「神様へのお詫びとご恩報じが大切です。それには人の難儀を助けることです」と説きました。賄いの仕事で時間のないきんは、山名分教会が神殿普請中と聞き、ぜひ普請に使っていただきたいと10円のお供えを申し出ます。藤沢はそれを上級へ運び、三日三夜のお願いに掛かると、ひさは自分の足で立てるようになりました。きんは神様の存在を実感し、なおも教会へ通い続けると、ひさは駆け回って遊ぶまでにご守護いただきました。
ところがその後、ひさは病を再発し、13年の生涯を閉じます。きんは、いま一歩のところで神様に縋りきれず、気を緩めたと悔やみました。ひさの出直しに続き、長女・まさが失明の恐れもある眼病に罹り、これにはきんも肝をつぶしました。きんは目の平癒を願い、どこまでも神様に縋りきり、自分にできることならどんなに難しい道も通らせていただこう、と思い至るのでした。
明治37年、弥市郎は台湾の阿里山トンネルの工事を請け負い、大倉組の幹部と共に300人の労働者を引き連れて海を渡ります。きんも台湾へ渡るべく、目が治ったばかりのまさと共に汽車で神戸港へ向かいました。
その車中、きんはひさの身上に際し、神様に立てた「どんなことをしても、おさづけの理を戴き、神様の御用を勤める」との誓いが気にかかっていました。
きんは一度は船に乗りますが、いよいよ出航のドラが鳴ったとき、「神様との約束をいま果たさなければ、一生果たすことができないかもしれない」との思いが頭をかすめ、目覚めたように、まさに「お母さんは急に用事を思い出したから、ひと便遅れて行くからね。心配しないでいい。お父さんをよろしく頼んだよ」と告げ、タラップを駆け下りていきました。「お母さん、どこへ行くの」と必死に叫ぶまさの声が耳に残ります。きんは、後ろ髪を引かれる思いを振り切り、人混みの中へ姿を消しました。こうしておぢばへ帰って別席を運び、38歳でおさづけの理を拝戴しました。
夫に反対されながらも
明治39年11月、きんは台湾へ渡りますが、弥市郎の怒りは容易に解けず、村の外れにある祠の軒先で休みました。しばらくの間、昼間はまさと共に炊事場で働き、夜間は祠で過ごしました。
弥市郎の愛人も台湾に来て、昼は炊事場でつとめ、夜は夫と過ごしている様子でした。きんは、教祖のような寛大な心には到底なれないと思い、鬱々として過ごします。やがて敵対感情を改め、自身の足りないところを補ってくれる神様からの使者だと思い、「あんたがいてくれるから、私は好き勝手にできる。布教にも出ることができる」と感謝の意を述べました。彼女もその真情を理解し、きんを「お姉さん」と呼ぶようになりました。
しばらくして弥市郎は、きんに宿舎へ移るよう命じます。きんはお社を据え、朝晩拍子木を打って、おつとめを勤めました。弥市郎は信仰を差し止めますが、きんは神様への誓いを守り、おつとめを続けるのでした。
ある日、炊事場で働く女性の息子の首に、真っ赤な腫れ物ができました。薬や祈祷でも治らず、お手上げ状態の女性を見かね、きんはおたすけを申し出ます。こうして渡台後、初めておさづけを取り次ぎました。三日三夜の二晩目の夜、膿が吹き出し、男児はたすかります。この話が地元の人々に伝わり、おたすけを願う村人がきんを訪ねて来ました。
阿里山の工事が終わると、弥市郎は嘉義の工事を請け負い、これに合わせて、まさは帰国して親戚の家で暮らすことになりました。嘉義へ移ると、弥市郎はきんを厳しく監視し、信仰に強く反対します。ある日、拝をしているきんの首を手ぬぐいで絞め、そこへ弥市郎の同業者がやって来て間一髪だったこともありました。こうした出来事を通して、きんは、神様が深い思惑のうえからたすけてくださったに違いないと思い、その不屈の信仰は一層強固になっていきました。
大正元(1912)年9月、きんは天理教校別科に入学します。別科では、教祖の道すがらを聞くたびに心が痛み、また心が晴れました。その後、長女・まさの家を訪ね、孫娘のくめを連れて台湾へ戻ると、弥市郎がマラリアの後遺症で入院し、見る影もなくやつれ果てていました。弥市郎は、きんに「おまえには長い間世話になった」と言うと、数日後、帰らぬ人となりました。
こうしてきんは、娘の身上を通してこの道に引き寄せられ、教えを実行し、神様のご守護を実感していきます。そして、夫に反対されながらも、神様への誓いを守り、おたすけを始めるのです。次回は、言葉の通じないきんが、どのようにして布教を展開したかを見ていきます。(つづく)
文・松山常教(天理教校本科実践課程講師)