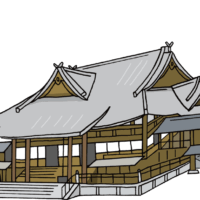豊かな実りにつながる丹精 – 綿のおはなしと木綿のこころ 第4回 草取り、摘芯
2025・7/30号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。

江戸時代から明治時代中ごろにかけて、綿作が盛んだった奈良盆地。20年近く綿の自家栽培に取り組む筆者が、季節を追って、種蒔きから収穫・加工に至るまでの各工程を紹介する。
多くの株で苞(花を包む葉)が付き、花が咲き始めています。5月3日に種を蒔いた綿は、ふた月半を経て70センチ前後にまで成長しました。
この時期の綿にとって心配なのは梅雨の長雨ですが、今年は梅雨明けが早く、その後は猛暑が続いています。おかげで長雨による根腐れの心配はなくなったものの、これからは水やりに特に注意が必要になります。そして、水やりとともに欠かすことのできない作業が草取り、間引き、摘芯、追肥です。

草取りとは、綿の株周りに生えている草を取り除くこと。間引きとは、一つの植え穴に2、3本生えている株を1本ないし2本にすること。摘芯とは、主枝の成長点を摘み取ることで、芯止めともいいます。摘芯によって側枝、実をつける結果枝の成長を促します。追肥は「ついひ」あるいは「おいごえ」と読み、一番肥、二番肥、三番肥と称して、その施肥時期や肥の種類、量を詳しく記している江戸時代の農書もあります。当地では本葉が2、3枚出てきたころに少量の有機混合肥料を株周りに施しています。これまでの経験によるもので、2回目の追肥は開花期に行います。
「おさしづ」に「育てば育つ、育てねば育たん」(明治24年3月21日)というお言葉があります。人を導き育てるうえでの丹精の大切さを諭されたお言葉です。労を惜しまず、世話することで農作物の豊かな実りにつながることと重なります。
ところで、『正文遺韻抄』に次のような一節があります。
「御承知の通り、大和の国は木綿が名産の一つであります。よその国によりましては、幼い時から、女でも籠をせおつて、草かりにでる所がござりますが、大和では、草かりといふ事はあまり致しませぬ。只今では、普通教育が盛んとなつて、皆学校へ通ひますが、以前では、大概拾二三歳になりますと、木綿の白機を織らしましたのでございます。夫故、はたごも、子供がのぼられるやうにできてをります。で、御教祖様は、八九歳のころ、既にこのはたごへのぼつて木綿をおおりなさる事は、たくみでおあり遊ばされたのでござります」
江戸時代の初めごろからすでに綿作が行われていた大和では、江戸時代後期になると木綿織物業が隆盛し、老若男女を問わず糸を紡ぐ姿が見られたそうです。「大和・河内・和泉の三ヶ国の田家(農家)にてハ、女にかぎらず、男子もミな糸をつむぐなり」(『綿圃要務』、天保4年)と記されています。そして、その糸から反物を織る機織りを担ったのは、主に女性たちでした。
男の子たちがもっぱら田畑へ出て草刈り、草取りはじめさまざまな農作業を手伝う一方で、女の子たちは機織りの腕を磨くことに精を出すことが求められた時代。畑で綿を栽培し、糸を紡ぎ、機を織ることは家族にとって貴重な副収入を得ることにつながります。そして、女性たちはその傍ら家族の大切な衣生活を支えました。
「機織は暮しを支えるたいせつな女の仕事の一つであった。家族の衣類 仕事着・アイ着・よそ行き着物などは、女が暇をみつけては機で織り、着物に仕立てて用を足してきたのである」(『改訂天理市史』)。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』26「麻と絹と木綿の話」を理解するうえで、ぜひとも心に留めておきたい時代背景の一つです。
梅田正之・天理教校本科研究課程講師