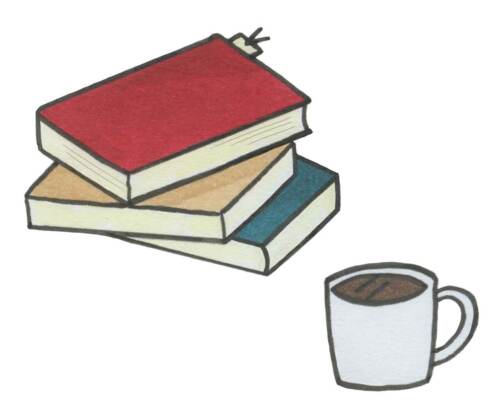レジですること – Well being 日々の暮らしを彩る 10
2025・9/10号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
宅配便を出しにいこうとしてドキリとした。財布がない……。いつも入れているカバンにも、他に置きそうなところにも。最後に見たのはどこでだったか。
ありありと目に浮かんだ。昨夜そうざいを買って帰った店のレジ前だ。駅の構内にある小さな店。荷造りの台はなく、支払ったその場でエコバッグに詰める。手をあけるため、レジ前にいったん財布を置いて、作業しながら「忘れそうだな」とちらと思った。で、案の定忘れた。
店に電話で問い合わせると、予想通り。遺失物は店でなく駅で保管することになっているので、そちらへ行くようにと。
「よかった。あって」。胸を撫で下ろす一方、愕然としている。傘や眼鏡ケースなど、忘れ物が多くなっている私だが、財布もとは。命の次に……とは言わないまでも、五、六番目には来そうな貴重品だ。
言い訳をすれば、忘れ物をしやすい要因はある。買い物のときレジで「すること」が格段に多くなった。コロナ禍で普及した非接触型決済と、時を同じくしてのレジ袋の有料化が大きい。
以前の私は少額なら現金で支払っていたが、いまや基本クレジットカードだ。そのクレジットカードも、前はレジ係に渡して処理してもらっていたのを、自分で機械に通すようになった。ポイントを貯めるカードもしかり。エコバッグへの袋詰めも自分である。
私のクレジットカードはタッチではなく、機械に差し込んで読み取りをする。交通系カードも兼ねているため、カードケースから取り出し挿入。急いてはいけない。処理完了の表示を確かめてから、抜いてケースへ。次いで財布からポイントカードを出し、機械に通せばなぜかエラー。「向きは合っているはず」。動揺を抑え、速さを変えてスライドさせて、ようやく成功。
いけない、やり直しで時間をとり、後ろに列ができている。慌てて荷物を詰めにかかる。レジ係もすでにレシートとポイント控えを差し出している。受け取って財布にしまう間もなく、エコバッグを持ち、逃げるようにレジを離れ……。
「すること」の多さに加え、求められる正確さ、待たせている焦りが、忘れ物を誘発するのだ。
駅に出向き、有人改札口で「忘れ物は……」と聞こうとして貼り紙に気づく。「遺失物保管所は×番ホームです」。忘れ物を取りにくる人がそれだけ多いのだろう。
コロナ禍までのレジ係がいかにマルチタスクをミスなくスピーディーにこなしてくれていたかを思い知る。さかのぼって感謝しつつ、忘れ物をしないよう注意力を養いたい。
岸本葉子・エッセイスト