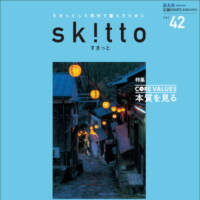祖母の想いを受け継いで – わたしのクローバー
野口良江(天理教栄基布教所長夫人)
1977年生まれ
おばあちゃんっ子
私は、自他ともに認める大のおばあちゃんっ子だ。祖母とは、私が高校に進学して寮生活を始めるまで一緒に暮らした。
初孫だったこともあり、ずいぶんかわいがってもらった。子供のころは、バスに乗って隣町のハンバーガーショップやラーメン屋さんに連れて行ってくれた。母が車の運転免許を取ると、大好きな地元の温泉にも一緒に通うようになった。
大人になってからは、帰省するたびに私の運転で買い物やランチに出かけた。祖母のリクエストで、一緒にボウリングをしたこともある。一人で天理に来たときには駅前のドーナツ店でお茶をする、そんなオシャレなおばあちゃんだった。
祖母はまた、嗜むことにも長けていた。俳句に詩吟、書道に茶道。なかでも俳句には特に力を入れていた。
月に一度、オシャレな背広を着たおじさま方と、すてきな装いのご婦人たちがわが家に集まってきて、句会が催された。お茶を出すのを手伝ったあと、みんなが持ち寄ったお饅頭やお煎餅など、子供にはちょっと渋めのお菓子を頂きながら祖母の傍らで過ごすその時間は、毎回とてもワクワクするものだった。
ありがたふ
祖母のもとには俳句仲間だけでなく、たくさんの人が訪れた。お茶菓子を持っておしゃべりをしに、悩み事の相談をしに、娘さんを連れて人生の節目の報告に……。
電話や手紙もまた然りだった。電話は相手の心行くまで話を聞き、手紙には毎回返信を書いた。時には返信を書きながら電話もする。一人ひとりに、それはそれは丁寧に対応していた。
寮生活を始めると私にも時折、手紙が届くようになった。毎回「ああ、おばあちゃんからやー」と実感する文字があった。
“ありがたふ”
祖母はいつも「ありがとう」をこう書いた。「ちょうちょう」を「てふてふ」と書く、その時代の人ならではだった。

大正生まれの祖母は、広島の出身だ。戦時中、疎開した福岡で天理教の女性布教師に出会い、信仰に目覚めた。自身も若くして布教師となり、宮崎県へ。霧島の山々が美しく見える町に、自らが信じたその教えを伝える地を求めた。
誰一人知り合いがいない所で、一人、また一人と声をかけ、心を繋いだ。やがて、その真実は実を結び、その地に教会を設立した。
祖母の実家は爆心地にほど近かった。実兄は原爆で亡くなっている。祖母に、復興した広島の街に行ったことがあるかどうかを聞いたことはない。
祖母は95歳まで生きた。葬儀の後、遺品の中に数冊のノートを見つけた。小さな俳句手帳を2冊、形見として大切に持ち帰った。90歳を超えてなお、句を嗜んでいたようだ。
「秋まつり母となる娘の里がえり」
私の部屋には、私と娘(ひ孫)のことを詠んだ句を飾ってある。
祖母が繋いでくれた生命を私は生きている。その想いもまた、しっかりと受け継いで。
おばあちゃん、ありがたふ。