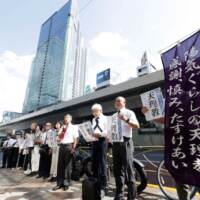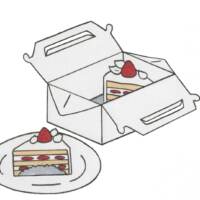親心がこもる「お下がり」に思う – 視点
2025・10/15号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
農林水産省の調べによると、令和7年産水稲の10アール当たりの収量は「前年を上回る」または「やや上回る」が13府県、「前年並み」が29都道府県、「やや下回る」が4県の見込みであり、主食用米の生産見込みは本年度の目標に向け、おおむね順調に推移している。また、平年単収で試算すると生産量は過去5年間で最大となる見込みであるという。今後の米の価格高騰などの問題はあるものの、有り難いことである。
ところで、毎年11月23日に宮中や全国の神社で行われる「新嘗祭」は、その年の収穫に感謝し、来年の豊穣を願う祭儀である。天皇陛下が新穀を天神地祀に捧げ、ご自身も召し上がる。これは全国の神社においても、古くから神に供えたものを下げて食することで、神々の恩頼を戴くことができると考えられ、この神人共食により、神と人とが一体となることが、直会の根本的意義であるといわれている。
本教においても教会などの祭典後の宴のことを直会と称している。本来は神道からの流れであり、祭典参加者が、お下がりの神酒、神饌を頂くという意味においては同じである。
筆者の教会でのこと。直会の席で、毎月のように「幸せな気持ちです!」と満面の笑みを浮かべる婦人がいる。祭典で日ごろ神様から賜るお恵みに感謝申し上げるとともに、おつとめ奉仕者が一手一つに世界たすけを祈願し、今月よりも来月にはもう少し成人しようとお誓いした後の、心清々しい、率直な心の声である。本来これが、お道らしい直会の姿なのかもしれない。
神様のお下がりに関する一思案であるが、教祖のお側でお仕えしていたという方が伝える話に、「お魚(川魚)なんか誰かが捕ってきて、料理して差しあげると、『結構やなあ』とおよろこびになって、ちょっとおあがりになって、(中略)『あとは、神様のおさがりとして、病人にあげてくださいや』」と仰せられたという(高野友治著『教祖余話』)。教祖がお召し上がりになられた、そのお下がりには、世界の人々をたすけてやりたいという親心がこもっているのだと思う。
現在、ようぼくが丹精するおたすけ先によっては、さまざまな事情で困難に出合うこともあろう。しかし、我々ようぼくは、どんなときも教祖のお言葉を信じ、神様のお下がりを持って、コツコツと地道なおたすけを第一に心がけたい。
(岡本)