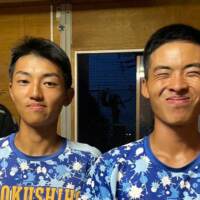火水風の恵みを頂いてこそ – 綿のおはなしと木綿のこころ 第5回 開絮、収穫
2025・8/27号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
江戸時代から明治時代中ごろにかけて、綿作が盛んだった奈良盆地。20年近く綿の自家栽培に取り組む筆者が、季節を追って、種蒔きから収穫・加工に至るまでの各工程を紹介する。
綿が実を結び、はじけ始めました。綿は花が咲いた後、子房が膨らみ、固い緑の実を結びます。そして、開花後40~60日ほどで実の表皮が裂けて、中から白い繊維があふれ出てきます。これがいわゆる綿花です。
一つの実には20~30粒前後の種が入っており、その一つひとつの種から生えている毛の集合体が綿花です。植物学的には綿の実は蒴果、繊維があふれ出てくることを開絮と呼ぶそうです。江戸時代は綿の実をその形状から「桃」、表皮が裂けて繊維があふれ出てくることを「綿が吹く」と表現しました。「棉吹く」「桃吹く」は、秋の季語にもなっています。
綿の吹き初めは、今年の当地では8月8日。ちなみに2024年は8月14日、2023年は8月11日でした。これはいずれも和綿で、洋綿は例年、和綿よりも数日遅れて吹きはじめます。二十四節気を細かく分けた七十二候に、「綿柎開」があります。綿が吹くころの意味で、8月23日~27日ごろを指します。開絮したばかりの蒴果はコットンボールとも呼ばれます。
綿花は湿気を嫌うため、吹いた綿は雨に当たらないように気をつけながら順次収穫していきます。これが綿摘み、綿取りです。摘み残しのないように摘み取るには、ちょっとしたコツがいります。また、乾燥して固くなった表皮は先が尖っていて肌を傷つける恐れがあり、茂った葉の中に手を入れることもありますので、収穫作業の際は手袋を用いることがあります。時間帯は朝露に濡れている午前中を避け、十分に乾燥した午後、できれば夕方が理想的です。
教祖が綿摘みをされていた様子が、『稿本天理教教祖伝逸話篇』に記されています。
「教祖は、綿木の実から綿を集める時は、手に布を巻いてチュッチュッとお引きになったが、大層早かった」
1「玉に分銅」
和綿は花が下を向いて咲き、実も下を向いてはじけるため、摘み取るときは指先で綿花を優しくつまみ、素早く一気に下にひっぱります。繊維が綿の殻に残らないようにリズム良く摘み取る様子を「チュッチュッ」と表現されているのだと思います。
また、上村福太郎著『教祖の御姿を偲ぶ』には「綿摘み」と題して次のような話が収められています。
「昔、中山さんの綿畠が今(編註・昭和23年当時)の上之郷詰所のところあたりにあって、教祖は夕方まで綿摘みをしておいでになり、北田と畠が隣同士だもんでよく話をしたそうです。祖母は『大へん美しい優しい方じゃった』と言っておりました」
おそらく、このとき教祖は、午後から綿畑へ出られ、夕方まで綿摘みに精を出しておられたのでしょう。摘み取った綿を竹籠に入れて背負い、軽やかな足どりでお屋敷に帰られるお姿が目に浮かぶようです。
農事の喜びの一つは、やはり収獲にあります。野菜や果物であれば、食べてもらった人からの「おいしい」のひと言が、どれだけ励みになることでしょう。綿花は食べることはできませんが、大ぶりで真っ白にふっくらとはじけた綿花は、まさに綿菓子のようでおいしそうです。
綿の豊作、不作には、その年の天候が大きく関わります。綿の実が膨らむ時期には晴天と適度な水、収穫期には何より晴天が続くことが望ましいとされるものの、天気は人間にはどうすることもできません。火水風の天地自然の恵みを頂いてこその収穫です。
いよいよ、綿吹く季節を迎えます。一つでも多く、“おいしそうな綿花”が収穫できることを楽しみに待ちたいと思います。
梅田正之・天理教校本科研究課程講師