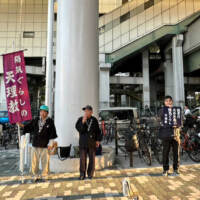縁を次代へとつなぐ意義 – 視点
2025・11/26号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
先ごろ、天理大学とドイツ・マールブルク大学による4回目の「共同研究プロジェクト」が天理で実施された(天理時報10月29日号既報)。マールブルクから5人の研究者がおぢばに帰り、二日間の学術研究発表と討論が意欲的に行われ、天理大宗教学科の教員らと共に、本部海外部から米国や英国の大学院で宗教学を修めた2人の中堅研究者が参加した。
冒頭、マールブルク大のトーマス・ウナス学長のビデオメッセージが流された。その中で、中山正善・二代真柱様の功績により、宗教学の分野で両大学の深い縁が紡がれたことにふれられた。
1960年、二代真柱様がマールブルク大で開かれた「国際宗教学宗教史会議」に招聘され、英語で研究発表をなされた。以後、学術研究をはじめ、さまざまな分野で交流が深まっていく。その間、中山善衞・三代真柱様が、また、真柱様がマールブルクへ足を運んでくださり、親交と縁が代を超えてつながってきた。
今回の「共同研究プロジェクト」では、「宗教との邂逅――旅・紀行・もの」のテーマのもと、二代真柱様が海外巡教での交流について綴られた書物が研究対象として扱われ、その広く、温かいまなざしにあらためてふれ、天理大創立100周年の節目に相応しい原点回帰の機会となった。
後日、マールブルク大の博士から「今回の知性に溢れた、そして心温まる個人的な邂逅の濃密な体験に、皆心を打たれていました。この交流が今後も継続されることを望んでいます。次回は、若手の研究者たちを天理から招いて、新たなチャプターの扉を開きたい」とメールが届いたという。
“ポストコロナ時代”にあって、海外へと雄飛しようとする気概が日本人の意識の中で薄まっているように感じる。海外の人々とのふれあいを通じて、一れつ兄弟姉妹の親和を育む「真心溢れる」邂逅を夢描く若者が増えてくることを願ってやまない。
(永尾)