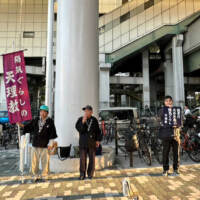国会の論議は何を誤ったのか – 手嶋龍一のグローバルアイ 51
2025・11/26号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
米ソの冷たい戦争が続く時代、筆者は予算委員会を舞台に華々しく繰り広げられる与野党の安保論戦をニュースにしてきた。野党の花形議員が時の総理にからめ手から迫って新たな政府見解を引き出す。その総理答弁を捉えて「従来より半歩踏み込んだ解釈だ」と報じたものだった。当の野党議員からは「よくぞトップ・ニュースに仕立ててくれた」と握手まで求められたことがある。野党側にとっては平和憲法から遠ざかった政府見解が示されたのだが――。冷戦下のニッポンは、米国の圧倒的な軍事力に守られ、心地いい「温室」に身を置いていた。そのため、国会という名の「箱庭」でかかる呑気な論戦が許されていたのである。
だが、時代は大きく回転し、台湾海峡のうねりは年ごとに高まっている。日米両国が瞬時でも対応を誤れば、たちまちグローバルな戦争に転化しかねない。もはや「箱庭」で台湾有事に関する想定問答など許される環境にはない。にもかかわらず、野党の外相経験者は、台湾周辺の海上封鎖のケースを示して、保守派総理から強硬な見解を引き出そうとした。70年代の初め米国のニクソン政権は、中国と劇的な接近を試みるに際し、「台湾問題の平和解決を希求する」と共同声明に謳って、有事の武力行使には触れようとしなかった。だが、この“曖昧戦略”には、中国が台湾に軍事侵攻すれば伝家の宝刀を抜くことを躊躇わないという決意が行間にそっと埋め込まれていたのである。
日本が台湾海峡で武力を行使する可能性を際立たせてしまった――今回の与野党の国会論議は、そんな役割を果たしてしまった。現下の苛烈な台湾情勢が、米国の“曖昧戦略”を突き崩しつつあるなか、ニッポンの箱庭論議はその自覚に乏しく、言の葉を弄んだのである。20世紀外交界の巨人だったキッシンジャーと周恩来が智慧の限りを尽くしてとりまとめた“曖昧戦略”。その当事者キッシンジャー氏に詳しい経緯を聞いたことがある。「きみは“曖昧戦略”というが、そこに曖昧さなどありはしない」と語った。台湾有事の芽を封じる仕掛けが施してある以上、何人も“パンドラの箱”を開けることなど許されないと言いたかったのだろう。