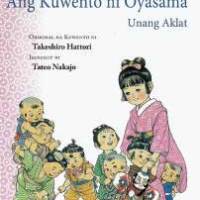目に見えん徳いただきとうございます 山田こいそ – 信心への扉

教祖の「ひながた」というのは、神様のお言葉に、次のようにあります。
「難しい事は言わん。難しい事をせいとも、紋型無き事をせいと言わん。皆一つ/\のひながたの道がある」(おさしづ・明治22年11月7日刻限御話)
この「おさしづ」は、『稿本天理教教祖伝』の「第八章 親心」をしめくくるお言葉です。「ひながた」は、「通らなければならない」というよりも、わたしたちが「通りやすいように」と心を配り、じっさいに通って示してくださった「親心」そのままの「ひながた」であるといわれるのです。
この「明るく暖かく涯知らぬたすけ一条の親心」にふれた道の先人は、どのような中も強い信念をもって歩まれました。
形のある物は

山田こいそ(嘉永4〈1851〉年〜昭和3〈1928〉年、旧姓・山中、のちにいゑと改名)の信心は、文久4(1865)年に、母そのが命のないところをたすけられたことに始まります。父は山中忠七。こいそは14歳でした。
大豆越村の山中家は、子守唄にも歌われた裕福な家です。忠七は毎日おやしきへ、お米を一升ずつ袋にいれて運ばれました。教祖とともに、どん底の道中にあったこかん様は、お喜びになったということです。
こいそは、5男4女の次女として生まれましたが、姉妹は夭折し、一人娘として大事に育てられました。22歳で従兄と結婚しますが、二人の子どもをのこして離縁されるのです。
婚家も裕福な家でした。けれども結婚生活は、しあわせなものではありませんでした。
明治11年、28歳の正月から、13年の暮れまで丸3年を、教祖のお膝元で過ごされます。御髪をあげたり、お着物を縫ったりと、身のまわりの御用をつとめ、教祖は「こいそはん」と呼んでくださいました。
教祖のお住まい、お召しもの、お食事は、たいへん質素なものでした。
教祖は、あるとき、
「目に見える徳ほしいか、目に見えん徳ほしいか。どちらやな」
と、おたずねになりました。こいそは、
「形のある物は、失うたり盗られたりしますので、目に見えん徳頂きとうございます」
と、おこたえになっています。
しあわせは、家柄や財産といった形あるものよりも、目に見えない徳をいただくところにある。世界一れつをたすけるため、貧に落ち切ってお通りくださる親心を、身にしみて感じておられたとおもうのです。「こいそはん、神様がカボチャの御守護くださったからカボチャの御飯炊いてや」とおっしゃる教祖のご飯は、カボチャばかりで米粒は数えるほどしかなかったという話が伝えられています。
ここが、親里やで
教祖のお膝元で、いつまでもお仕えさせていただきたいと決心されていた中に、3年に3度、山田伊八郎から人を入れて、こいそを嫁に、というお願いがありました。
3度目にお伺いされると、教祖は、「嫁入りさすのやない。南は、とんと道がついてないで、南半国道弘めに出す」というお言葉をもって、お許しになるのです。明治14年、そのお言葉をいただいて、こいそは、倉橋村出屋鋪(現在の桜井市大字倉橋)の山田伊八郎と結婚します。伊八郎は、それを機に、生涯の信心を心に定め、夫婦でおたすけにはげみました。
明治15年、教祖は、出産のちかいこいそに、「今度はためしやから」と、をびやの試しをなさいました。そして「ここがほんとの親里やで」と、お産の後は、里の両親のもとへは寄らず、教祖のもとへすぐに帰ってくるようにといわれました。
こいそは、家の人がいない間に産気づき、じぶんの前掛けを畳の上に敷いて、かるがると女の子を安産します。そして、家人の帰宅までに、じぶんで子どもにお湯をつかわしました。この不思議なご守護に、家人も隣人も、みながびっくりしたということです。
そして、お産から三日目には、雨上がりの道を高下駄を履いて、赤児は伊八郎が抱き、倉橋村から14キロを歩いておやしきへ帰りました。
「もう、こいそはん来る時分やなあ」とお待ちくだされていた教祖は、たいへん喜ばれ、赤児をお抱きになり、いくゑと名づけてくださるのです。
当時、お産は穢れであり、さまざまな禁忌(タブー)がありました。その中にあって、常識よりも、親なる神様のお言葉を信じきって通られたのです。


人をわるく言わんよう
伊八郎は、身上や事情に出合うたび、教祖から親しくお話を聴かせていただき、その場で書きとりました。それは、教祖がこいそにお聞かせくださったお話でもあります。
その克明な記録は、いま、『根のある花・山田伊八郎――先人の遺した教話(3)』(道友社新書)によって読ませていただくことができます。
そこでは、親神様が元のやしきにおいて人間と世界を創められた、元初りのお話ばかり語られています。そして、心を澄まして、きれいな心になるということを強くさとされています。
明治17年4月9日(旧3月14日)の項をとりあげます。こいその右足が痛むので伊八郎がおやしきへ帰ると、教祖は、すぐにお話を聴かせてくださいました。お話には、「人を腹立ささず。人を腹立させば、人また我を腹立さし。
人をうらみな。人をうらみたら、人また我を、うらみたり。
人に物を買うときは、代価をねぎりな。
また人に物を売るときには、かけね、ゆいな。
人に、そんをかけたら、人また我に、そんをかけるべし。
人の事(わるぐち)を、ゆわんようにせよ」とあります。そして当時、警察の干渉がきびしいので、教祖を留置する役人の足が立たぬように、おやしきの門の内へも入れぬようにされたらよいのにと申したところ、その後、足痛になる。これを思案せよ、と添え書きがあります。
一れつ人間は、みな神の子、お互いは兄弟姉妹である。これをよく思案して、人をわるく言わんよう、といわれるのです。
教祖の「先になると、このやしきで暮らすようになるのやで」というお言葉どおり、明治44年からは、伊八郎の本部員登用にともない、懐かしいおやしきで懸命につとめました。「教祖から南半国の理を授けられたのやから、わしは七度生れかわっても、この理を生かして見せる。でないと教祖に申しわけない。尊い理をいただいたとは言えん。三人前の働きではまだ足らん、十人前の働きするのや」と語り、「おふでさき」を、老眼鏡をかけて読まれるのがつねであったといわれます。
どのような中も、教祖のお心をもとめ、心を澄まして通りきられた姿勢をうかがうことができます。
文:伊橋幸江 天理教校本科研究課程講師