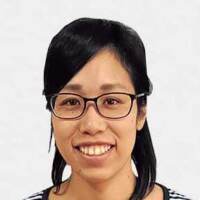令和の短歌ブームに思う – 視点
「『この味がいいね』と君が言ったから七月六日はサラダ記念日」。この歌で知られる俵万智の歌集『サラダ記念日』は、昭和62(1987)年に出版され、280万部のミリオンセラーとなった。それから35年経った令和のいま、和歌(短歌)が若者を中心に再びブームになっている。
『サラダ記念日』出版の同年に始まった東洋大学主催の「現代学生百人一首」には、昨年、過去最多となる7万8千首以上の応募が国内外の学生からあった。また、出版不況のなか、岡本真帆の『水上バス浅草行き』をはじめ、若手歌人の歌集がしばしばヒットしている。
背景には、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の存在がある。SNSへの投稿は、雑誌や新聞などの歌壇よりも敷居が低いようだ。すぐに「いいね」で反応を知ることができ、限られた文字数で発信する点でも、SNSと短歌の親和性は高く、自作の歌をネット上に投稿する若者が増えているという。
また、和歌が時代を経て幅広い層に親しまれてきたのは、31字という小さな形式による作りやすさと覚えやすさにある。だからこそ、雅な王朝世界にとどまらず、武士や庶民に教養を与え、茶道や狂言等の技芸を教え、商売の心得を垂示するためにも用いられた。古典和歌からの脱皮を図った明治以降の近代短歌作家も、圧倒的多数が五七五七七の音数定型を維持した(浅田徹著『和歌と暮らした日本人』)。表現される場面や言葉が現代的になったとしても、いまなおその形式が踏襲されている。
さて、明治2年から執筆された「おふでさき」は、「耳に聴くだけでは、とかく忘れがちになり易い人々の上を思い、筆に誌して知らされた親神の教」(『天理教教典』)である。それはまた、「何人にも親しみ易く、覚え易いようにと、歌によせてものされた」(同)ものであり、五七五七七の和歌体をもって教示されている。初めて教えを聞く当時の人々への親心をあらためて感じるとともに、私たちも日ごろから「おふでさき」に親しませていただきたい。
(三濱)