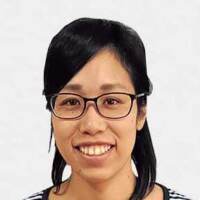第40話 ぼくたちはずっと一緒だった – ふたり
沖のほうからやって来た波が、小さな潮の泡をまき散らしながら波打ち際を進んでくる。そして途中で力尽きて、あきらめたように海に帰っていく。再び海面が盛り上がり、鈍色の波が「今度こそは」という感じで進んでくる。
寄せては返す波の調べに心が静まるのは、人間の身体のどこかに、遠い海辺の記憶が残っているせいかもしれない。カンもハハも、海辺で癒やされていった。波が去ったあとの、帯状に広がった濡れた砂が、午後の日差しに淡く光っている。
遠い街で暮らすさとしは、ときどきメールに添付した写真を送ってくる。そこには人のいない公園の遊具や、放置された自転車などが写っている。彼は写真を撮ることで自分を癒やそうとしているのかもしれない。送られた写真を、カンはプリントして、お菓子の空き箱のなかに大切にしまっておく。いつか写真に人や動物が登場すればいいなと思っている。
会いにいってみようか。
ふと、そんなことを思ったりもする。すっかり大人になったツツの面影が、いまも彼のなかに残っていた。それは冷たくて熱い不思議な感覚をもたらした。
秋も終わりに近づいた日の朝、カンはいつものように波乗りに出かけた。外気と海水の温度差が激しいと、海面から水蒸気が昇る。朝焼けが霞んで見える。波はきれいに整えられたラインをつくり出している。彼は海と一つになって最適な波を待つ。
この季節には台風もやって来ない。乾燥した風が吹き、澄み切った青空の下での波乗りが可能になる。だから休みの日には、多くのサーファーたちが海に繰り出す。さらに季節が進んで、午後の早い時間から波の斜面がキラキラ輝くようになると、もう冬の訪れが近い。こうして一年が過ぎていく。
海から上がると、彼はボードを抱えて砂浜を歩いていった。店じまいをした海の家のまわりに、船底を上にしたボートが引き上げられている。風が当たらず、砂が動かないところには、ハマヒルガオやツルナなど、砂浜で花を咲かせる植物の群生が見られた。
砂地を被う草花のなかに、小さな黒い塊がうずくまっていた。近づいぬいてみると、生まれて間もない仔犬だった。彼はサーフボードをそっと砂の上に置いて、仔犬のそばにしゃがみ込んだ。前から予感していた。帰ってくることはわかっていた。こうしてきみを見つける前から、ぼくたちはずっと一緒だった。
「ピノ」
声に出して呼びかけた。仔犬はわずかに首を上げて青年を見た。
「おかえり」
(終)