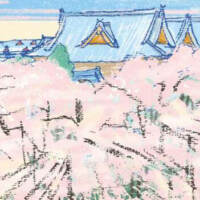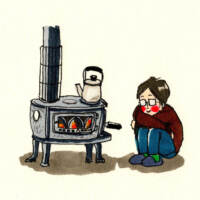「教祖誕生祭」の意義を思う – 視点
2024・4/3号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
昨年5月にコロナの感染症法上の位置づけが「5類」になったことで、親里の諸行事もこの1年で徐々に以前の姿を取り戻しつつある。そして今月は、いよいよ教祖誕生祭が行われる。祭典後には、縮小を余儀なくされていた「よろこびの大合唱」が再開されるとのことで喜ばしい。
教祖誕生祭は、昭和8年10月に現在の教祖殿が竣工したことから、翌9年4月、教祖の136回目のご誕生日に勤められたのが始まりだ。
最初の誕生祭を前に挨拶に立った松村吉太郎本部員は、これまで人類の母親、お互いの救いの親なる教祖のご誕生日に対して、今日まで記念すべき奉祝祭典のなかったことは、教祖に対してなんとも申し訳ないと述べたうえで、「本日の御誕生日を心からお祝い申し上げると共に、今日の御誕生日に新たに存命の御教祖を偲び教祖ひながたの道を肝に銘じて当時の熱烈なる信仰に立ち帰らねばならんと考えるのであります」と、誕生祭を勤める意義を闡明した。誕生祭には、教祖存命に対する実感と信念を堅固にする意味合いがあったのだ。
ところで、先日ある講習会で教祖について講義をする機会があった。講義の終わりに受講者の感想を尋ねると、20代前半の方から「いままで教祖は空想の人物だと思っていました。教祖は本当に実在されていたのですね」と意外な言葉が返ってきた。理由を尋ねると、「教祖のことは漫画でしか知らなかったから」と。この答えに愕然とした。
考えてみれば、いまの若い世代の周囲には、ネットの充実もあって、漫画、アニメ、映画、ドラマと、フィクションが溢れている。これらのメディアコンテンツは高い娯楽性が求められるので、歴史上の人物に対しても、あらゆる脚色を施した作品づくりがなされている。こうしたものに日常的に親しんでいる環境では、誤解してしまうのも無理からぬことだ。
しかし、こういう時代だからこそ、毎年ご存命の教祖のご誕生日を皆で心からお祝い申し上げる誕生祭の意義は、より大きくなっていると感じる。
(諸井)