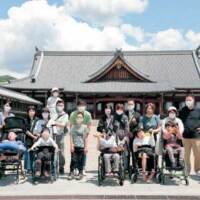第14話 助けを求める力 – ふたり
少年は月に一度か二度、母親と一緒にやって来た。カンは彼を車に乗せて、あちこちへ連れていった。海へ行くこともあれば、省吾さんの農場を訪れることもあった。そのあいだ母親のほうは、ハハとともにレストランの仕事を手伝った。
名前を、さとしという。もうすぐ小学五年生になる。わたしは彼をカンの子どものころに重ね合わせてみる。あのころのカンは、いろんなことに興味をもっていた。虫に夢中だったこともある。本ばかり読んでいたこともある。いつも何かに夢中だった。
さとしは反対である。どこへ連れていっても、何を見せても興味や関心を示さない。ただぼんやりして、そこにいるだけだ。喜んでいるようにも、楽しんでいるようにも見えない。どんな感情も表に出すことがない。省吾さんの農場へ連れていったとき、怪しいやつが来たと思ったのか、例の茶色の雑種犬が吠えかかった。さとしはなんの反応も示さなかった。
母親によると学校での勉強に問題はないらしい。それどころか成績はクラスでも一番か二番なのだそうだ。学校の勉強や成績が、いかに当てにならないかわかる。誰が見ても、この子は問題を抱えている。新太などに比べると、とても健康に育っているとは思えない。こんなにぼんやりしていては、ちゃんと生きていけるかどうか心配だ。
「専門のスタッフに相談したほうがいいと思うけどな」。ハハは言った。「あの人の話を聞いていると、ご主人のことを根はやさしくていい人だと思っているみたい。実際、さとし君にはやさしくて、よくお土産なんか買ってくるんだって。いいことかどうかわからないけど。いちばんの問題は、夫が暴力を振るうのは自分のほうに原因がある、と本人が思っていることね。彼女がそういうふうだと、さとし君だって混乱してしまうんじゃないかな。どんな理由があっても、暴力は暴力なんだから。悪いことなんだと、はっきり教えなきゃ」
命なんて不公平なものだ、とわたしは思った。やさしかったトトがあんなに早く亡くなり、自分の息子を病人にしてしまうような男が生きながらえている。
「相談するのが怖いのかもしれない」。そう言って、ハハは複雑な表情でカンを見た。「知られると、また暴力を振るわれるから。彼女のほうも、さとし君と同じように、自分を表に出すことができなくなっているのかもしれない。助けを求める力を奪われたら、その人は生きていけない」
わたしはハハの口調にトトを感じた。彼女がいま話しかけている相手は、カンであるとともにトトであるような気がした。ハハの目には、誰がどんなふうに映っているのだろう?