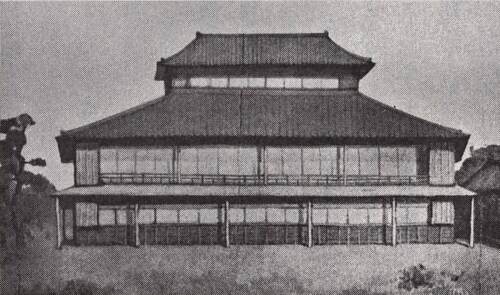揺るがぬ心で丹精に尽くし 諸井その(上) – おたすけに生きた女性

今回紹介するのは諸井そのです。安政4(1857)年、静岡県袋井に住む父・小坂源六、母・孝の3女として誕生。明治8(1875)年、のちの山名大教会初代会長・諸井国三郎と結婚し、2男6女を授かります。娘の身上をきっかけに入信し、布教に奔走する夫の留守を守りつつ、おたすけに励みます。33歳のときに半身不随になって以降も、たんのう一条に通り、晩年は、おやしきの御用に尽くしました。そのは「山名の道の母」とも呼ばれ、教会伸展の土台となりました。
子育ての傍ら家業に励み
そのの実家は、先代から料理兼宿屋を営んでいました。13歳まで手習いに通い、14歳で渡辺能登守という旗本へ奉公しました。2年ほど勤めて家に戻り、裁縫の稽古に通い、明治8年に19歳で国三郎と結婚します。
夫・国三郎は天保11(1840)年、静岡県袋井の農家の3男として誕生。17歳のとき侍奉公を志して江戸へ上り、旗本へ仕官し、明治維新の激動期を生き抜きます。34歳のとき、故郷で農業を礎とした国産を興そうと決意します。
そのと結婚した国三郎は、奉公人を雇い入れ、養蚕、製糸、機業を始めます。そのは子供を育てながら家業に励みます。一から始めた事業だったため、糸を引くにも機を織るにも、ずいぶん難儀したと後年、語っています。
国三郎は所用が多く留守がちでした。国三郎が戻ると、そのは家の切り盛りや家業のことで相談を持ちかけるのですが、太っ腹な気質の国三郎は、「おまえのよいようにしろ」と言って構ってくれません。反物を売るのも、糸や染め草を買うのも大抵そのの仕事で、目まぐるしい毎日を送っていました。
明治15年10月、商用で東京の八王子へ派遣した番頭が、帰路で知り合った吉本八十次を連れて戻ります。八十次は、しばらく諸井家に住み込んで働くことになりました。この吉本八十次が、初めて遠州に“道の種”を蒔くのです。
2カ月ほどしたころ、織物の教師・井上マンが歯痛で二日二晩苦しみ通しました。気の毒に思った八十次は、「神様にお願いしてあげましょう」と、水の入った茶碗を持ってきました。そして「いま、月日様にお詫びをしてきました。これをお上がりなさい。疑ってはなりませんよ」と言って、マンに手渡します。それを飲むと眠りに入り、翌朝、マンの歯痛はすっかり治まっていました。
これを聞いた国三郎は、どういう信心か八十次に尋ねました。八十次は、自身が眼病をたすけていただいた話から、十柱の神様のご守護、かしもの・かりものの理、八つのほこりの教えを説きます。国三郎は深く感じ入りますが、従業員を抱えて事業を営む責任から、すぐに信心するわけにはいきませんでした。
八十次が、痛風に2年間苦しんで寝返りもできないという人のおたすけに掛かると、三日三夜の願いを三度継いで、九日目に歩けるようになりました。「神様見たような人が来た」と八十次の評判は広まり、臍が腐って虫が湧いていた子供をはじめ、7、8人の難病の人がたちまちたすかりました。
そのうち八十次は、毎年おやしきの正月の鏡餅を搗かせてもらっているので大和へ帰ると言い置いて、諸井家を去りました。

夫の心を動かした固い決意
それから間もなく、国三郎の3女・甲子(2歳)が咽喉気を患い、声も出ず、乳も飲めず、医者も難しいという重篤な容態となりました。そのは、八十次から聞いた神様におすがりするよりほかに道はないと思い、国三郎に信心することを懇願します。ところが、国三郎は「おまえの信心は、腹の空いたのを徳で治そうというものだ。そんなことで治るものか」と諭しました。生来、温厚で逆らったことのない無口なそのが、このときばかりは何を言われても折れず、談じ合いは3時間に及びました。
最後に、国三郎が「医者にかけないが、それでもよいか」と問うと、そのは「よろしゅうございます」ときっぱり答えました。そのの固い決意に心を動かされた国三郎は、「それなら、おまえの言う通りにしよう」と、信心する心を定めました。後年そのは、この時ほど嬉しいことはなかったと述懐しています。そのの揺るがぬ心が、山名の元一日を生みだしたのです。
神棚に水を供え、夫婦で一心不乱にお願いすると、その夜のうちに娘は乳を飲むようになります。翌朝には声を出し、三日目にはご飯に汁をかけて食べられるまでにご守護を頂きました。
明治16年2月10日、国三郎はお礼参りにおぢばへ帰りました。教祖は「神の方には倍の力や」と仰せになり、神の自由をお示しになって、国三郎に力を入れて信心するよう促されました(『稿本天理教教祖伝逸話篇』118「神の方には」)。
国三郎は、おやしきで八十次と再会します。八十次は喜んで応待しましたが、国三郎がおぢばへ引き寄せられるのを見届けるかのように、その後、行方は分からず、二度と会うことはありませんでした。
やがて、八十次にたすけられた人々の間で、講を結んで信心しようという気運が高まり、同年2月26日、11人の信者で講社を結成。講名は「天輪講」と名づけられ、国三郎が講元になります。これが山名大教会の始まりです。
「お金も衣類も、何もいりません」
翌月、高井猶吉、宮森与三郎、井筒梅治郎、立花善吉が遠州を訪れました。4人がおたすけに出ると、不思議なたすけが相次ぎました。国三郎のもとで働く教師や工女たちは、おてふりを教わり、神様のお話を聞かせてもらいました。これを機に、講名が「遠江真明講」へと改称されます。
深い教理と十二下りのてをどりを仕込んでいただかねばならぬと感じた国三郎は、再びおぢばへ帰り、二下り目から十二下り目までを、わずか4日間で習得しました。そして、飯降伊蔵を通して「国へ帰ってつとめをすれば、国六分の人を寄せる。なれど心次第や」との神様のお言葉を頂き、感激に胸打たれるのでした。
講社の数が倍増し、国三郎が東奔西走するなか、そのは夜もろくに寝ずに働き、留守を守りました。このころから、事業は天候不順や物価下落の影響を受けて行き詰まりを見せていました。そのは国三郎に、こう言いました。「いくら働いても、これでは楽しみがありません。いっそ商売をやめて、わずかでも農業をしながら、信心に来るお方をたすけさせていただく方が、よろしゅうございます。もうお金も衣類も、何もいりません」
このひと言が国三郎の心を動かしました。「おまえの言う通りにしよう」と言って廃業し、道一条に踏みきります。
おたすけを願う人が日々多く訪ねてきましたが、国三郎は、おたすけと負債の整理のために留守がちでした。代わりに、そのがお話を取り次ぎ、三日三夜のお願いをさせていただくと、不思議におたすけいただきました。近郷一帯への伝道は、そのの丹精に依るところが大きいといいます。
不思議なたすけが次々と現れる一方で、生活は窮乏していきます。機織の道具や衣類などをだんだんと売って、布教費と生活費にしました。それでも夜遅くに信者がやって来ると、そのは近所から借りてきた米を搗いてまかない、味噌で醤油を拵えるなどして、温かくもてなすのでした。
こうしてそのは、自らの固い決意をもって信心する心を定め、さらなるおたすけに生きる道へと歩みを進めていきます。この後、思いがけない大節を通して、生涯末代にわたる指針を授けていただきます。次回は、二人がその節をどのように乗り越え、歩んでいったかを見ていきたいと思います。(つづく)
文・松山常教(天理教校本科実践課程講師)