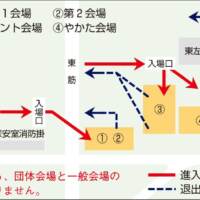世界に誇れる親里の食文化 – 視点
料理やスイーツのおびただしい情報が連日メディアに流れている。それらは希少な食材を使用したり、いわゆる“SNS映え”する盛り付けをしたりすることで付加価値を高めている。
こうしたなか、国連世界観光機関(UNWTO)等が主催する「ガストロノミーツーリズム世界フォーラム」が今月、奈良で開催される。ガストロノミーツーリズムとは、その土地の気候風土が生んだ食材・習慣・伝統・歴史などに育まれた食を楽しみ、土地の食文化にふれることを目的とした旅行だ。持続可能な観光としてUNWTOが推進しており、コロナ後の新しい旅行スタイルとしても注目されている。
天皇から庶民まで幅広い層の人たちの歌が収録されている日本最古の歌集『万葉集』をひもとけば、古来、わが国では野の菜はもとより、山の幸から海の幸まで多種多様なものが食されていたことが分かる(廣野卓著『食の万葉集』)。
また、歴史地理学者の伊藤寿和氏によれば、興福寺一乗院門跡の坊官が記した戦国末期の日記『二条宴乗記』等の史料からも、大和国では多彩な山菜類や果物類が食されてきたことがうかがえる。
親里では、教祖140年祭への三年千日のスタートとなる来春、教祖ご在世時から続くお節会が3年ぶりに実施される。お節会の始まりは明治初期、正月に供えられた餅を、お屋敷に帰ってくる信者や村方の人にも分けて食べさせてやりたいとの教祖の親心にある。
各地の教会で搗かれたお供えの鏡餅は、1月4日の鏡開きで小餅に切り分けられ、お節会当日に焼かれて、水菜を添えたすまし雑煮として振る舞われる。飾り気のない簡素な雑煮だが、そこには教祖の親心を受け継ぐ大勢の道の子の真心が込められている。
こうした目に見えない心にも思いを寄せるとき、寒中の親里で頂く一椀は、より一層味わい深くなるだろう。それは、人類のふるさと・ぢばに帰った者しか味わえない、世界に誇れる食文化と言ってよい。
(三濱)