新しい年、国際社会といかに向き合うか – 手嶋龍一のグローバルアイ 拡大版
2022年は、波乱の予感に満ちて幕を開けようとしている―――。国際政局の行方を読むことを責務としている筆者のような者がそう断じた年は、意外にも何事もなく過ぎ去ることがある。そうあってほしいと心から願っている。
だが、国際社会の眼はいま、二つの軍事大国の動向にじっと注がれている。「習近平の中国」は、海上に空母機動群を、上空に新鋭の戦闘機・爆撃機群を、そして宇宙に量子暗号衛星を配して、隙あらば台湾を「一国二制度」の名のもとに呑み込もうとしている。
一方の「プーチンのロシア」もまたウクライナ国境に10万人規模の精鋭部隊と正体不明の特殊部隊を集結させ、ロシア人が多く住むドンバス地方などを切り取る構えをみせつつある。
中ロ両大国を率いる独裁的な指導者は互いに連携しながら、「バイデンのアメリカ」の持てる力を東アジアと欧州に引き裂こうとしている。去年秋に中ロの合同艦隊が津軽海峡に姿を見せたのは決して偶発的な出来事ではない。
東アジアの民主主義陣営を代表するニッポンはいまこそ、永年の同盟国である米国さらには豪・印・西欧諸国とも連携して対中包囲網を整え、中国の力による侵攻を断固として抑止すべきだと思う。
道義の力、文化の深さ
だが、軍事力によって北京を牽制だけでは決して十分とは言えない。世界が「民主主義」と「強権主義」に切り裂かれつつあるいま、われわれは道義が持つ力を決して軽んじてはならない。いまの中国にも軍事力によっては世界の人びとを心服させられないと考える人々がいるからだ。隣国、中国をいかに理解すればいいのか―――。
かつて、われわれは竹内好という思想家を探照灯として中国を理解しようとした。竹内好は早くも戦中に名著『魯迅』を著し、列強の植民地支配に抗う現代中国の挑戦を魯迅というひとりの作家の内面に分け入っていくことで描き切った。その竹内好が、いまこそ読まれるべき文章を遺している。「こういう場合に中国人はどう考えるか、という問題を私が自分に課する時、私はそれを、あなたはどう考えるか、という風に翻訳して考えている自分に気がつくことがよくありました」(「中国人のある友人へ」より)
日中戦争のさなかに官費留学生として北京で暮らした青年、竹内好が偶々知り合って友となった無名の若き読書人こそ、彼の中国理解の揺るぎない座標軸となったのである。
「文化の深さは、蓄積の量ではなく、それが現在にあらわれる抵抗の量によって測られるということ」を、この北京の友人が体現していたのだが、北京にいた当時の竹内好青年はそれに気付かなかったと愧じている。
「とくに文化問題として気づいていないこと、私があなたをいたわるつもりであなたを傷つけていたのが、文化にたいする私の理解の浅さからくるものであったということを、私はさとりました」
魯迅が仙台医学校の恩師、藤野厳九郎先生の写真を掲げて筆を執ったように、竹内好もまた北京の友の筆になる南画の小幅とタゴウルをこの友人が漢訳した詩を交互に書斎に架けて原稿に向かったという。現代中国が列強の植民地支配に抵抗する精神を文化の力として喝破したひとは竹内好を措いて他にいないだろう。
竹内好と北京の友人が存命なら、「習近平の中国」の振る舞いをどんなにか悲しむに違いない。いまや「習近平の中国」は、内に在ってはウイグルやチベットの少数民族を弾圧し、外に在っては台湾を力で併合しようとしているのだから。だが、草の根の中国人が蓄積してきた抵抗の量は短い間に消えはしないはずだ。竹内好がいう「文化の深さ」は、やがて強権体制を内側から突き崩す原動力になると思う。
◇
新しい年、われわれが道義のさらなる高みに立つことで、中国人の内面に育まれてきた抵抗の文化と連携する時が到来した。迂遠に映るそんな試みこそが、忍び寄る台湾有事を未然に防ぎとめる決め手になるかもしれない。いたずらに反中国感情を煽りたて、軍備の増強を叫ぶだけでは、隙あらば台湾を「一国二制度」の名のもとに呑み込もうという北京の術策に却って嵌ってしまう。中国の片隅に我らが同志は必ずやいると信じたい。
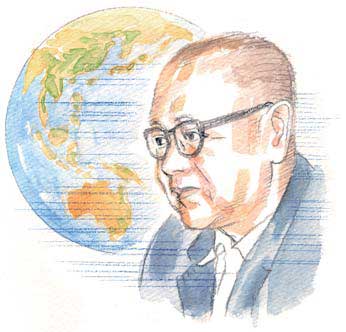
竹内好(1910―1977)中国文学者、思想家。東京帝国大学文学部支那文学・哲学科卒業。魯迅の研究と翻訳で知られ、日本文化の近代主義を批判する評論でも活躍。戦時下に刊行した最初の著書『魯迅』は、その後の魯迅研究に大きな影響を与えた。





