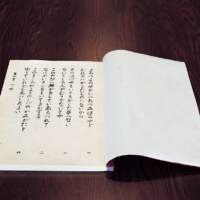政界に渦巻く“派閥”とは – 手嶋龍一のグローバルアイ38
2024・9/11号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
日本ではいま与野党の党首を選ぶ“政治の秋”を迎えている。保守政治の主役をながく担ってきた派閥の大半が、政治資金スキャンダルに見舞われて解散に追い込まれた。そのさなかに行われる総裁選挙だけに、日本の政界にも地殻変動が起きるのか海外からも関心を呼んでいる。
アメリカの政界にも日本のような派閥はあるのか 若者からそう尋ねられることがある。民主政治の先駆けをつとめた米国にも「コーカス」と呼ばれる黒人議員連盟などはあるが、それは自民党内の派閥とは全く異なる。米連邦議会には、法案の採決に際して政党の側が所属議員を拘束する規則がない。議会に諮られる法案は、連邦議員一人ひとりが自らの判断で賛否を決める。ましてや民主、共和両党の大統領候補選びでは政界のボスの意向など誰も聞かない。
翻って、議院内閣制を敷く日本では、法案の採決にあたって党議で拘束が課され、総裁選びでは派閥の領袖が子分たちの票をがっちりと押さえてきた。これこそが派閥の究極の存在意義なのである。派閥を牛耳るボスは、総裁選びで力を存分に発揮し、その見返りに子飼いの部下たちにカネとポストを用意してきた。だが、米政界が先進的で、日本政界が遅れていると言いたいのではない、大統領制と議院内閣制の違いゆえに独自の政治風土が生まれたのである。
しかし、日本の有権者は、内閣総理大臣を選ぶ至高の権限を国会議員に託したはずだ。その貴重な一票が派閥の領袖に牛耳られていいはずはない。自由民主党の総裁選への立候補には20人の国会議員の推薦が必要だ。それゆえ、旧来の派閥が中心となって、推薦人を確保し、票をまとめるような事態となれば、スキャンダルで大半が消滅したはずの派閥が息を吹き返すことになりかねない。旧来の派閥はいまや政策集団に衣替えしたと主張する候補者もいるが、総裁選びで旧来型の領袖が復権する余地を残しては意味がない。「総裁に選ばれれば派閥を離脱する」と表明する候補者も現れた。これでは一国の総理大臣を選ぶ権限はひとまず派閥に頼り、その後に派閥のくびきから脱するという詭弁に聞こえてしまう。