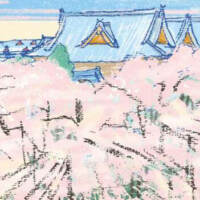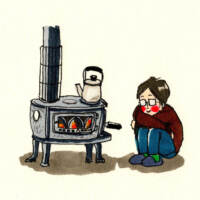タイで2回目の教育支援 小学校などで“特別授業” – 天理大学「国際参加プロジェクト」
2024・4/3号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。

天理大学国際交流センター室が主導する第20回「国際参加プロジェクト」は、2月12日から28日にかけてタイ王国の3都市・県を拠点に実施された。同国での実施は昨年に引き続き2回目。参加した学生11人は、現地の小学校など5校を訪問して教育支援を行ったほか、チャオプラヤ川の清掃活動を実施した。
同プロジェクトは、天理大学が標榜する「他者への献身」を国際的な舞台で実践するもの。2001年、インド西部地震の際に現地で救援活動を行って以来、アジアの発展途上国へ活動の場を広げ、災害救援や教育支援などを展開している。
「バディ」のサポート受け
12日に現地入りした一行は、オリエンテーションを経て、14日から東北地方マハーサーラカーム県にあるドンビエンチャン小学校で活動開始。タイ語による劇や折り紙の記念品づくりなど、日本文化にふれる”特別授業”を行った。さらに15日には、中高一貫校のマハーサーラカーム大学附属学校、翌16日には地域で少子高齢化が深刻な問題になっているバンメイヤイ学校で、それぞれ児童・生徒らと交流した。
この後、北部の都市チェンマイに続いて、首都バンコクを訪れた一行は、バンコク都環境局の協力のもと、チャオプラヤ川で清掃活動を実施。これは昨年、野口信也・タイ出張所長が、環境局長を務めていた旧友に協力を打診して実現したもの。学生たちは環境局員の清掃員と共に12隻のボートに分乗し、川に浮かぶ大量のごみを回収した。
なお、期間中、天理大学の交流協定校である大学で日本語を専攻する学生が「バディ」(相棒)として参加。マハーサーラカーム県では13人、チェンマイ県では7人が、天理大学生の通訳をはじめとする生活面のサポートを行った。
◇
参加した学生の一人で、今回プロジェクトリーダーを務めた山田友見さん(体育学部3年)は「バディと共に一つの目標に向かって協力し、互いの思いを尊重し合うことで、言葉や文化の壁を越えた、特別な絆ができたように思う」と笑顔を見せた。
同プロジェクト担当の関本克良・天理大学教授は「初めて海外に出る学生も少なくないなか、互いにたすけ合う場面がそこかしこで見られ、非常に有意義なプロジェクトになったと感じている。これからも、海外と日本の”懸け橋”となる取り組みを一層推し進めていきたい」と語った。