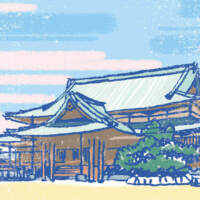薄明の朝焼けを仰いで 教祖のご期待を心に銘じ – 逸話の季
2023・7/19号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。

この数日、夜は窓を開け放して眠りに就き、そのまま朝を迎えるようになりました。目覚まし時計をセットしなくても、窓から差し込む朝日と、にぎやかな鳥の声で自然と目が覚めます。光と音に溢れた世界を満たす、親神様のご守護を味わいながら、今ここに生きていることを実感する季節です。
*
明治10(1877)年6、7月ごろのある日のこと。教祖は村田イヱに「オイヱはん、これ縫うて仕立てておくれ」と仰せられ、甚平に裁った赤い布をお出しになりました。教祖は、直ぐに縫い上げたそれをお召しになっていましたが、その日の夕方にイヱの息子の亀松(のちの幸助)が腕の痛みからお屋敷へ帰って来ると、「ここへ連れておいで」とお招きになり、「さあ/\これは使い切れにするのやないで。家の宝やで。いつでも、さあという時は、これを着て願うねで」と仰せになり、お召しになっていた赤衣を脱いで亀松にお着せくださいました
『稿本天理教教祖伝逸話篇』「五一 家の宝」
*
「家の宝」を頂戴した人々の喜ぶ姿が、目に浮かぶような逸話です。これまでに何度か『天理時報』の取材で赤衣を拝見させていただく機会がありました。その際に、いつも印象的だったのは、100年以上の時を経ても色褪せていない赤衣の鮮やかさです。
もちろん、教祖の赤衣を大切にしてきた人々の思いの結晶なのでしょうが、現在も褪せることのない赤色には、人類を明るい未来へ導き、その向かうべき道を照らしだす、教祖の親心を感じます。
*
私たちは教祖の赤衣を通して、教祖が「月日のやしろ」であり、その教祖の残されたお言葉やご足跡が、世界中の人々を「陽気ぐらし」へと導く“親神様のメッセージ”であると実感することができます。そして今日も、教祖は新しい赤衣に着替えて、世界中を駆け回っておられるのです。「さあ/\これは使い切れにするのやないで」との仰せは、特定の個人に対するものというより、「ようぼく」としての役割を期待されるすべての教友にとって、心に銘ずべきお言葉ではないでしょうか。
文=岡田正彦