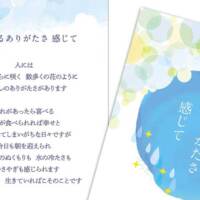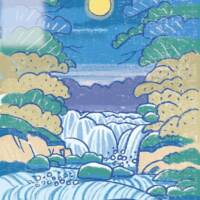「水の味」を求めて – 視点
2023・8/23号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
この夏も厳しい残暑が続いている。こうしたときにふと頭に浮かぶのが、「諭達第四号」にも引用されている「水を飲めば水の味がする」というお言葉だ。
これは、教祖が貧に落ち切る道中で述べられたお言葉である。『稿本天理教教祖伝』では、貧に落ち切ることを通して教えてくださった事柄について次のように記されている。
「物を施して執着を去れば、心に明るさが生れ、心に明るさが生れると、自ら陽気ぐらしへの道が開ける」
この意味するところについて、中山正善・二代真柱様は、風呂の譬えをもって明快に示されている。
すなわち、風呂に入るには服を脱ぐ必要がある。脱がずに入ることもできるが、気持ちよくなろうと思ったら裸にならなければならない。
それと同じで、物を施して裸になるのは、目的ではなく手段である。陽気ぐらしをする手段として、教祖は裸になられたのである、と。
二代真柱様が風呂の譬えを用いられたところに、深い味わいを感じる。先人には風呂にまつわる逸話が数多く残されているからだ。
たとえば、増井りん先生は「お風呂はナア、ぬくみ水気の御守護頂くのやで」と述べられ、浴槽につかると、まずおやしきのほうへ向かい、目を閉じてしばらく祈念してから、浴槽の湯を一口飲まれたと伝わる。
また、高井猶吉先生は、風邪のときでも「神様に温めてもらうんや」とおっしゃって、必ず風呂に入られたという。
「火と水は一の神」と教えられるが、親神様のご守護を象徴的に表したものが風呂であろう。しかしながら、そうしたご守護も、服を着たまま、いわば心に執着があっては感じることができない。
欲と高慢を捨て、心が裸になるところに「かりもの」の有り難さがありありと迫ってくる。二代真柱様は、このことを教えてくださったと思案する。
「水の味」を求めて、毎日を元気いっぱいに通らせていただきたい。
(山澤)