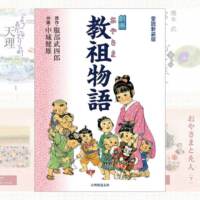原典をもとに考える“事情” – 視点
2024・1/24号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
石川県能登地方を震源とする大地震の被害の実態が日に日に明らかになるにつれ、被災者の苦難を想い、つい気持ちが沈みがちになる。
そこで、この事態を見せられた私たちの心の治め方について原典をもとに考えてみたい。
「おふでさき」には、「ぢしん(地震)」の語を含むお歌が二首ある。そのうちの一つが、
かみなりもぢしんをふかぜ水つきも これわ月日のざねんりいふく
「おふでさき八号58」
で、世の中の天災地変は、すべて親神の残念、立腹のお心が表れたものと教えられている。そのうえで、
この事をいまゝでたれもしらんから このたび月日さきゑしらする
「おふでさき八号59」
と、これから先に起こる天災は、皆そのように受け取るよう促されている。さらには、
月日にハみな一れつハわが子なり かハいゝばいをもていれとも
一れつハみなめへ/\のむねのうち ほこりいゝばいつもりあるから
このほこりすきやかそふぢせん事に 月日いかほどをもふたるとて
「おふでさき八号60~62」
と、親神にとって世界中の人間は皆わが子供である。ただ可愛いばかりであるが、皆の心にほこりがいっぱい積もっているから、このほこりをすっきり掃除しないことには、親神がどれほど子供のためを思ってもたすけることができないと、人間の親としてのもどかしい思いを明かされている。
この一連のお歌から思案するとき、現在、私たちがお見せいただいている〝事情〟は、私たちを含め、世界中の人間の心に、相当の「ほこり」が積もったゆえのことと思案しなければならない。
真柱様は4日の「年頭あいさつ」で、このたびの地震について「教祖の教えを信じ、教祖の道を通らせていただくお互いの、心の成人の鈍さに対する厳しいお仕込みであると思う」とお諭しくださっている。
教祖140年祭三年千日活動2年目の踏み出しに当たり、自らの心を澄まし、そして“道を広める決意”を新たにしたい。
(諸井)