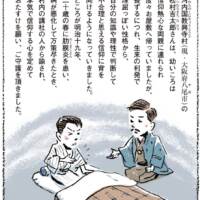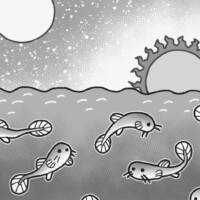愛用の万年筆で手紙をしたためる”祈りのひと時” – 家族のハーモニー
若き日の異国での経験が
私の事務机のペン皿には、6本の万年筆が並んでいる。亡き父や敬愛する義兄の形見、学生時代にアルバイトをして買ったもの、拙作の出版お祝いに頂戴したものなど、どれも思い入れが深い。
万年筆の傍らには、インクの瓶が5本並ぶ。私はブルーブラックの色が好きで愛用しているが、この5本はメーカーごとに微妙に趣が異なる。6本の万年筆は、ペン先が細いものから極太まであり、その時々によって万年筆とインクを選びながら手紙をしたためている。
たとえば、傷心にたたずんでいる人には、元気になるようにと願いを込めて、少し太めの文字を明るめのインクで、というように。相手は気づかないかもしれないが、日課に追われる日常で、私が大切にしている祈りのひと時でもある。
日ごろ私のスマートフォンには、多くの人から相談の電話が入ったり、悩みを打ち明けるメールが届いたりする。通話やメールのやりとりで事足りる場合もあるが、時には、きちんと文章にして伝えたいと思うこともある。
殊に、新型コロナウイルス感染症が流行し始めてからは、手紙を書く機会が増えた。定期的にお会いしていた人と会いにくくなったためでもある。
手紙を書いても一方通行の場合が多いが、「手紙着きました」とメールが来ればそれで十分だし、そのあとに感謝の言葉があれば、なお安堵の気持ちが湧く。たまに郵便受けに返信が届いたりすると、飛び上がるほど嬉しくなる。
若き日、私は妻と共に長期間、ブラジルで生活した体験を持つ。携帯電話もインターネットもない時代、国際電話は高額で簡単にかけられず、通信手段は手紙しかなかった。私と妻の、双方の両親とたくさん手紙のやりとりをした。
届いた手紙には私たちへの親心があふれており、それが筆跡やインクの染みからも感じられ、繰り返し読んだものだ。そうした経験が、手紙の大切さを知る原点になっていると思う。
ロイヤルブルーのインク
私は地域で保護司を務めており、数多くの青少年と付き合いがある。保護観察の面接を通して親しくなり、その後もメールなどで近況を知らせてくれる子供や親御さんも少なくない。
その一人であるT君は、関与してしまった事件のことで、いつも自分を責めていた。私は面接のたびに、彼の良いところを褒め、励ますことを心がけていた。
あるとき、肩を落として帰る彼の後ろ姿が気になり、その日の面接で話したことを、あらためて手紙で伝えることにした。その後、少しずつT君の笑顔が見られるようになった。
母親からも、「Tにとって生まれて初めてもらった手紙かもしれません。それが、あんなに自分のことを認めて応援してくれている手紙だったから、嬉しかったと思います」と電話があった。私の手紙を部屋の壁に貼り、毎日それを読んでから勤めに向かっていることを知った。
あの日から数年経った昨年、T君は、お付き合いをしていた彼女と結婚した。「コロナ感染症の蔓延で身内だけの結婚式だったけれど、本当は白熊さんに来てもらいたかった」と彼から電話があった。
その夜、私は彼に2通目となる手紙をしたためた。お祝いの気持ちとともに、この日を迎えるまでの彼の努力を讃え、そして今日まで陰から心を配り、支えてくれた母親へのお礼を忘れぬようにと、老婆心を添えた。
数日後、母親から電話があった。「Tが白熊さんの手紙を見せてくれて、『お母さん、今日までありがとう』と言ってくれたんです」と涙声で言われた。
彼に宛てたお祝いの手紙は、彼のために探し求めたロイヤルブルーのインクを使った。
白熊繁一(1957年生まれ 天理教中千住分教会前会長)