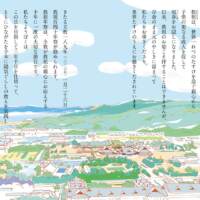“ハッピ文化”再考 – 視点
2023・6/21号を見る
【AI音声対象記事】
スタンダードプランで視聴できます。
天理教のハッピは明治22年、秋津系信者数百人が、そろいのハッピを着て土持ひのきしんをしたことが始まりとされる。その後、ひのきしんに限らず、参拝やおさづけを取り次ぐなどの改まった場面でも着用されるようになった。
ハッピは本教の“トレードマーク”でもある。ハッピ姿の人がひのきしんをしている様子を見て、未信仰の人が感銘を受けるということもある。一方で、ハッピ姿の人々が行き交う町の様子を初めて見た人から、「異様だ」といった否定的な声を聞くこともある。
果たして、ハッピは教外者、とりわけ初めて本教に接する人の目にどのように映るのだろうか。管見では、このような問いを立てた調査は見当たらない。
そこで筆者は、AIによる画像解析を行うカメラアプリを使って、ハッピがどのように認識されるのかを試してみた。同アプリは、撮影した被写体から得られる識別情報をもとに、関連する検索結果を表示する仕組みになっている。これを使って、「天理教」という文字が写るようにハッピ姿の人を後ろから撮影したところ、検索結果の上位に来たのは、黒地に白文字で「滅」や「天下無双」とあしらった画像であった。
もちろん、この結果だけでハッピの印象を判断するのは早計である。インターネット上には本教のハッピに関する情報が少なすぎるのかもしれない。また、形態的特徴ではなく心理的側面に着眼すれば、もともと宗教に対して抱いている感情が、それが正のものであれ負のものであれ、ハッピに投影されるのかもしれない。その他いろいろな視点から考察する必要があるだろう。
いずれにせよ、ハッピは自分の信仰を宣明するような服装であり、それを着る人は、自分の行動が他者からどう見られるのかを意識しておきたい。何より肝心なのは、ハッピを着ていようといまいと、ようぼくとしての自覚であり、「なるほど、お道の人は感心なもの」と言われるような日々の通り方を心がけることである。
(三濱)