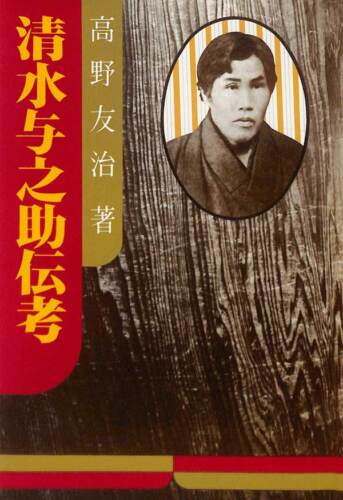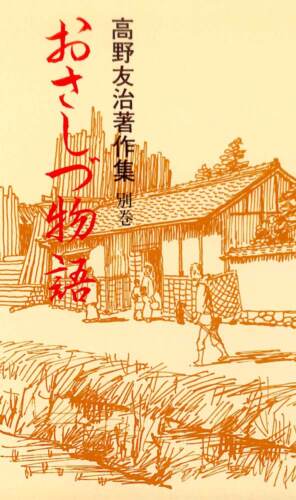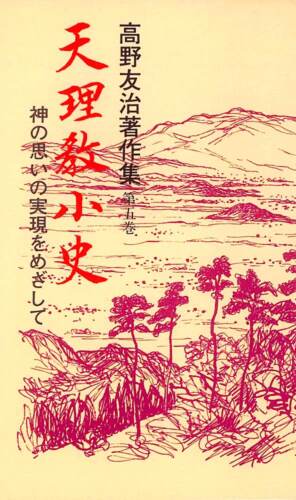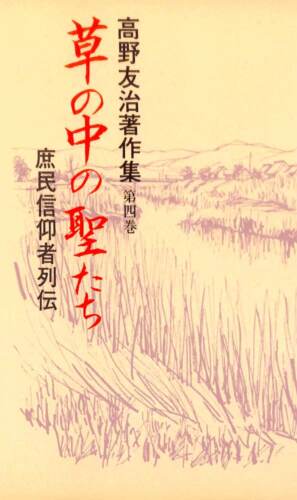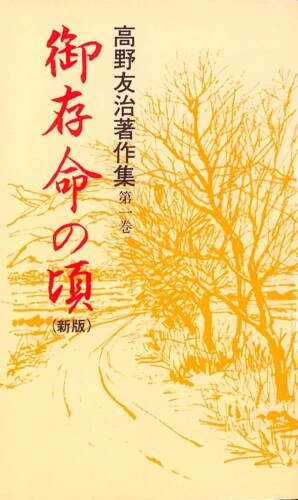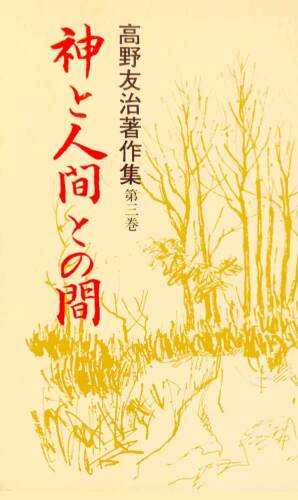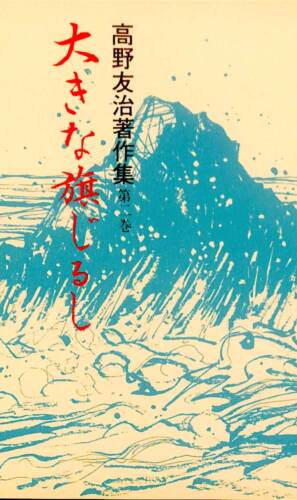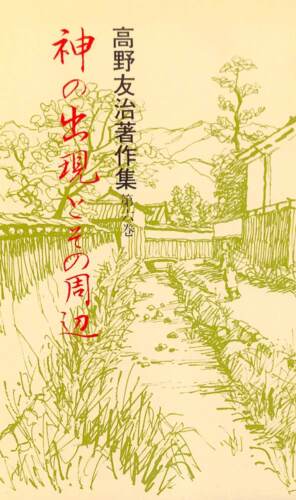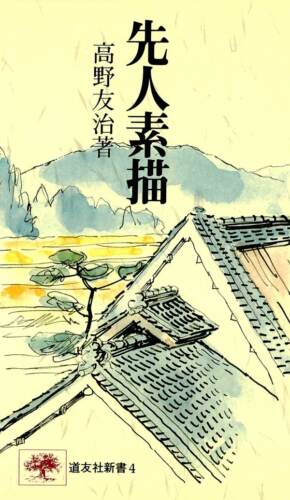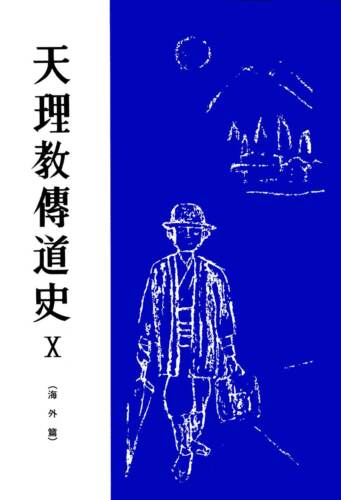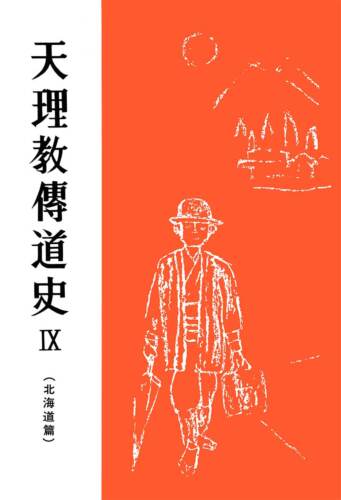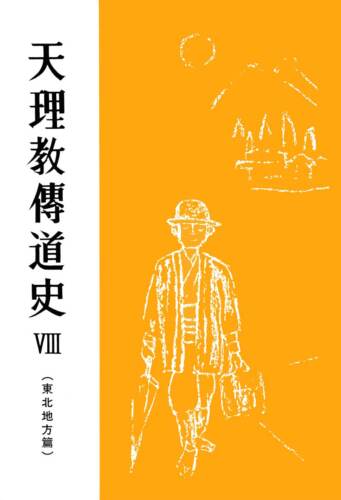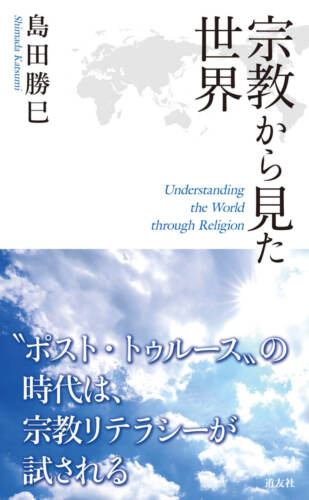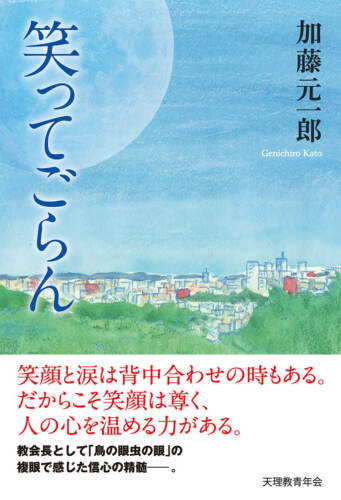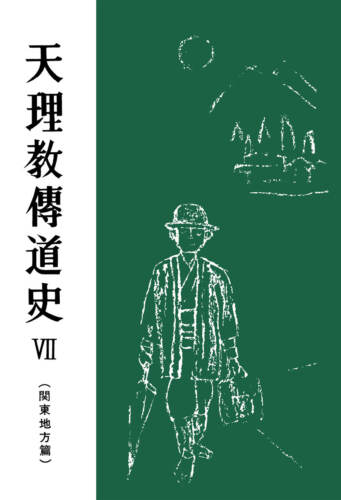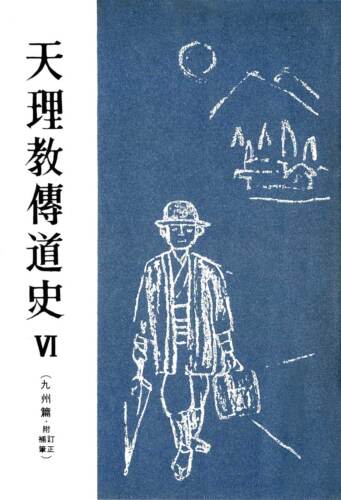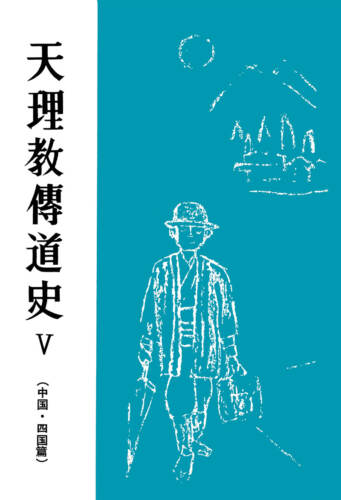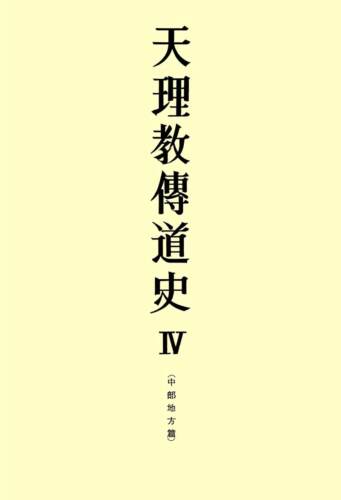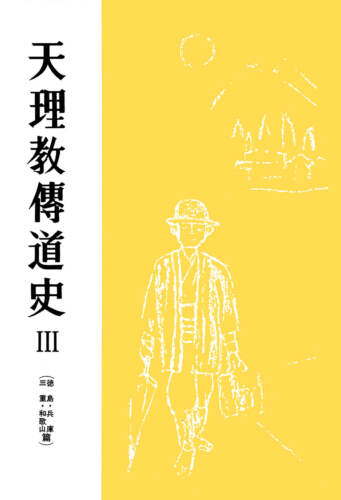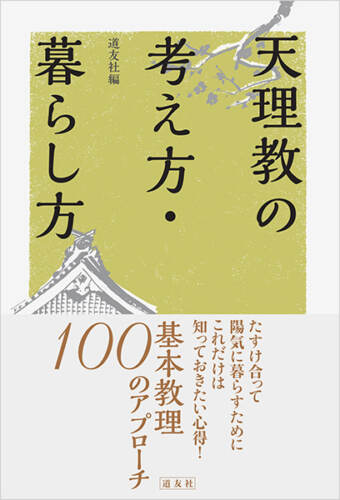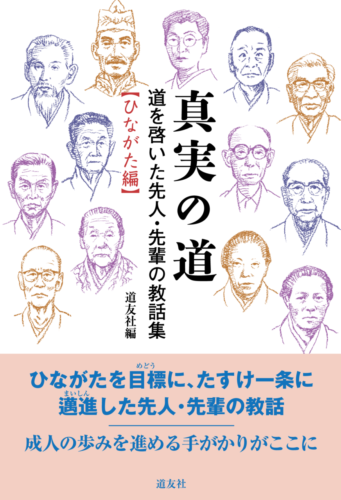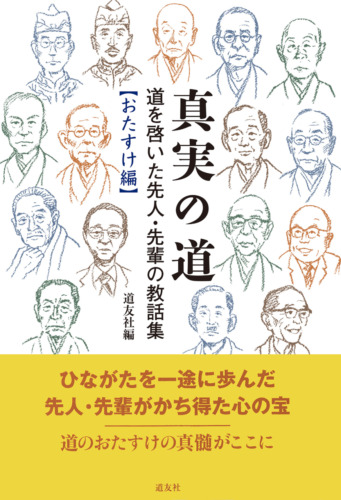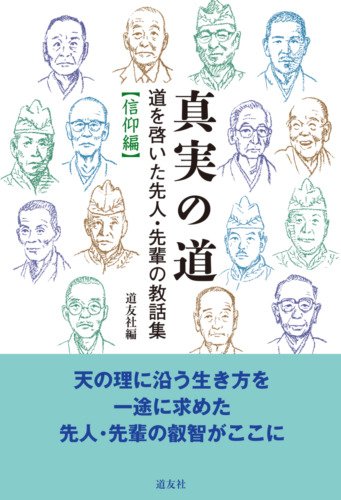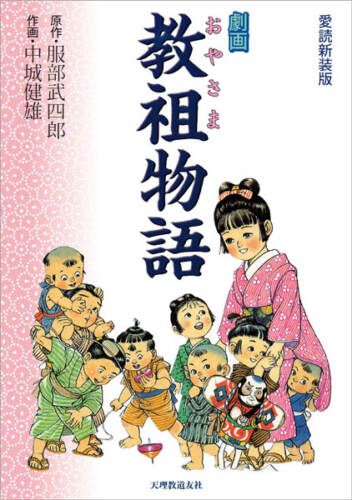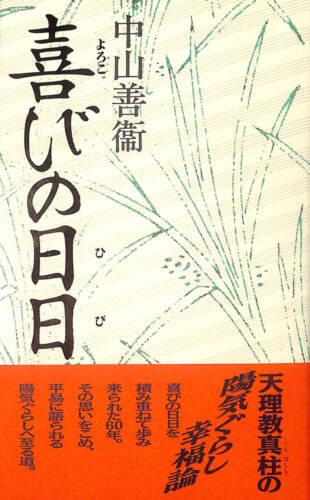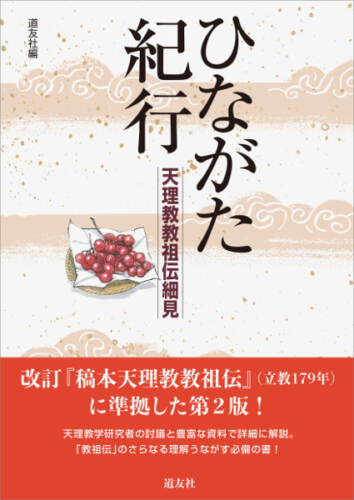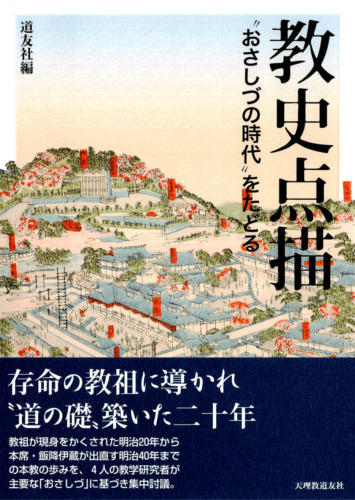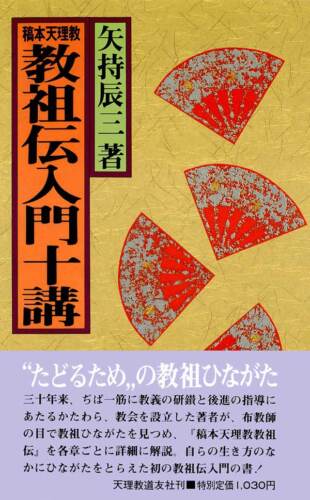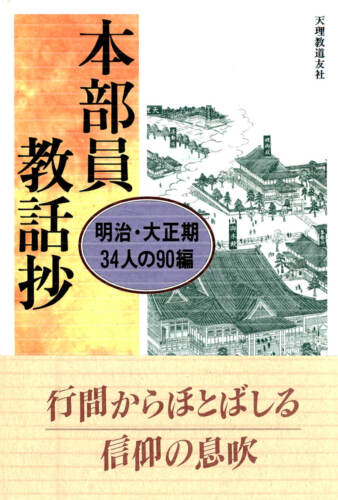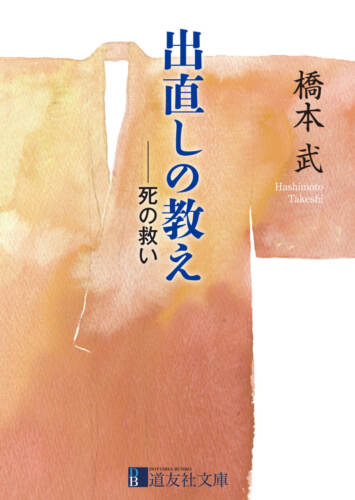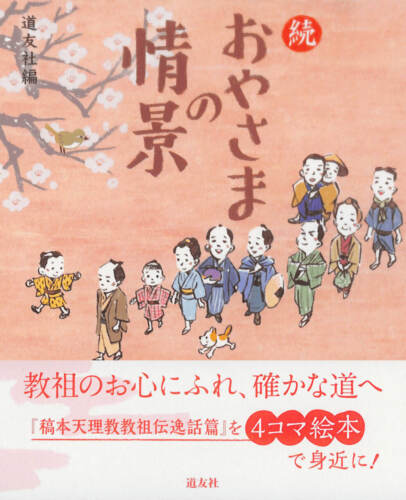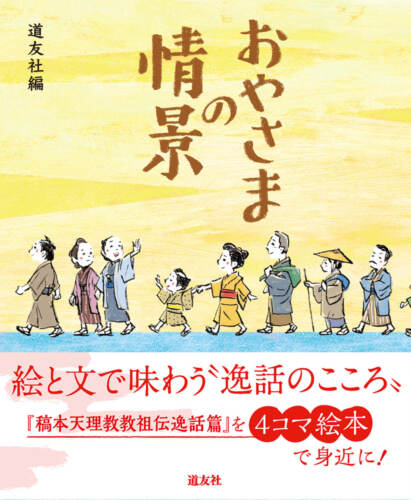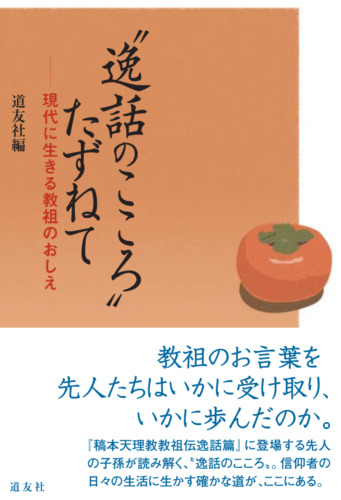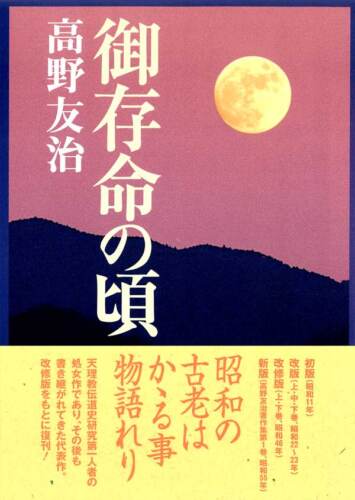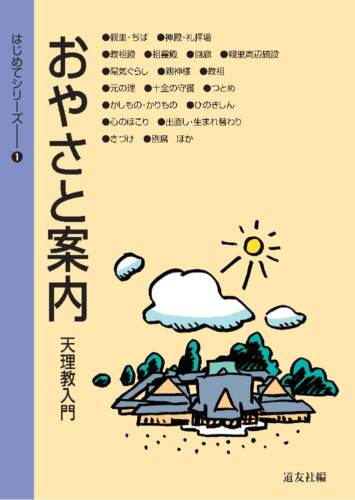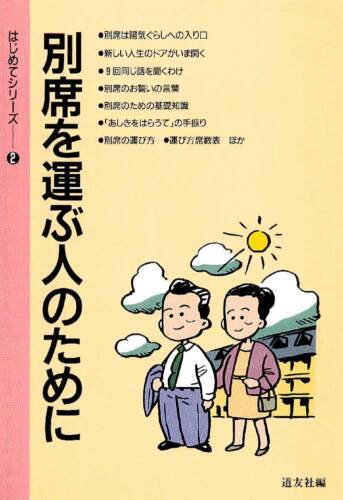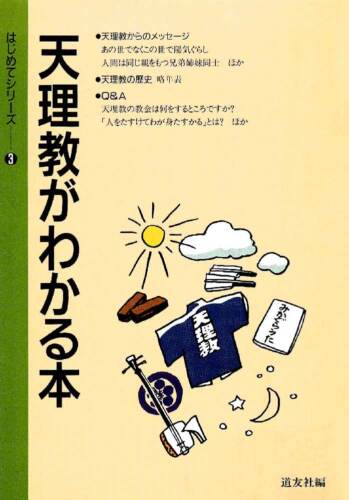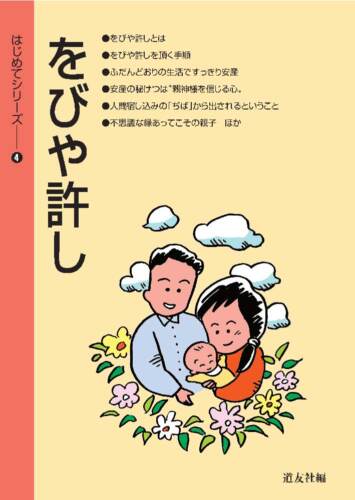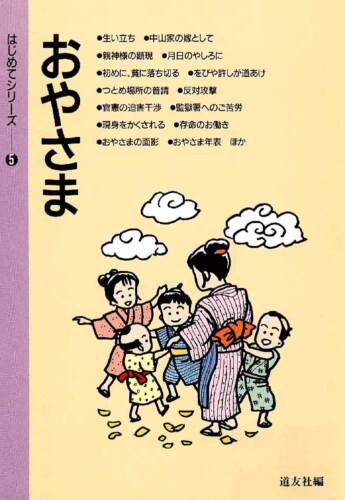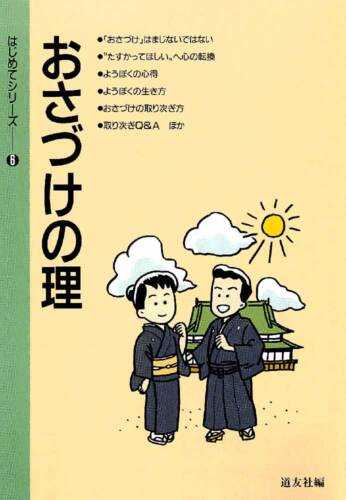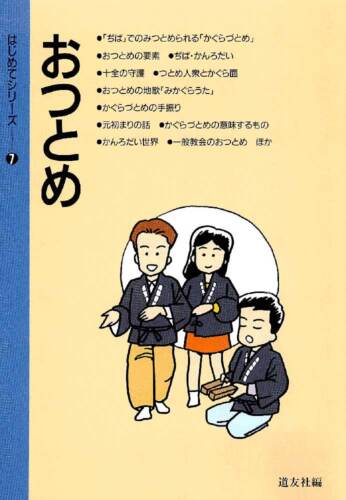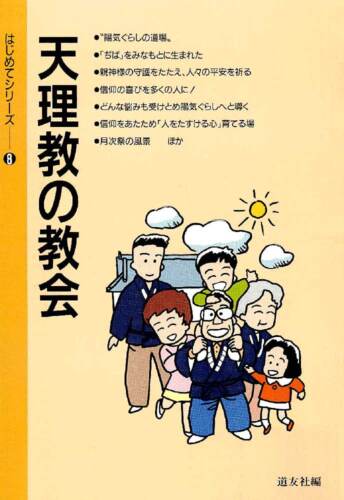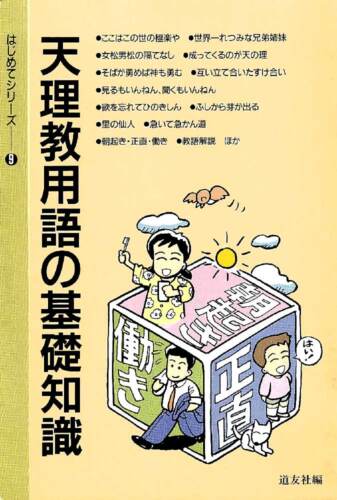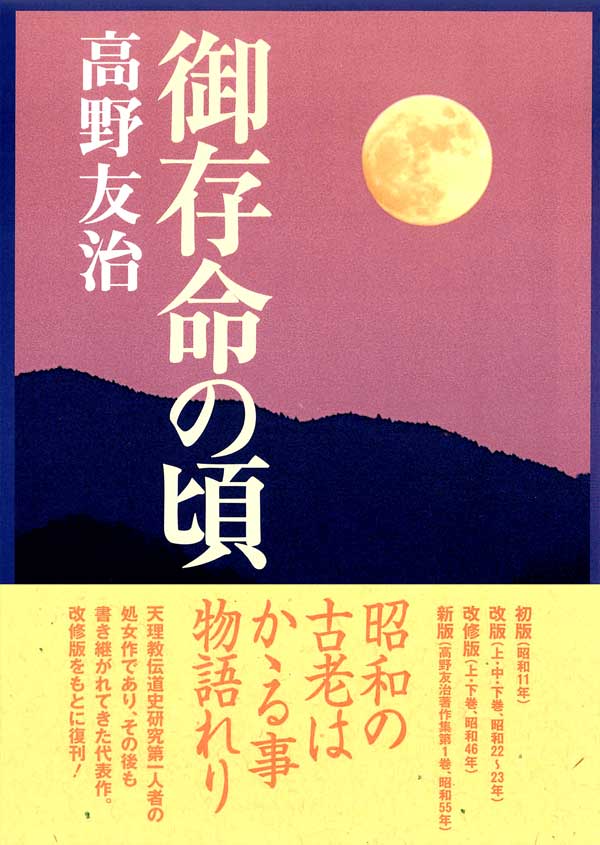
御存命の頃
本書は、天理教伝道史研究の第一人者であった著者の処女作であり、その後も書き継がれてきた代表作。昭和46(1971)年の改修版の一部を改め、全一冊として復刊しました。
2001年1月 発売
紙の本の価格:¥1,760(税込)
紙の書籍を買う
月額定額で電子版が読み放題!詳細はこちら
【著者プロフィール】
高野友治 (たかの ともじ)
明治四十二年、新潟県加茂市に生まれる。昭和七年、天理外国語学校(現・天理大学)英語部卒業後、天理教道友社編集部に勤務。教祖から直接教えを受けた古老を歴訪して昔語りを聞くとともに、その郷土に語り伝えられている語り草を収集して回る。十三年、天理教校本科へ移り、天理教史を教える。二十三年、天理大学に招かれ、三十三年、教授に就任。五十三年に退官後、天理大学名誉教授となる。主な著書に『御存命の頃』『天理教傳道史』(全十巻)『高野友治著作集』(全七巻)『先人素描』など多数。平成十五年、九十三歳で出直し。
- 序文
- まえがき
- 立教以前
- 一、御誕生のころ
- 1 日本および世界の情勢
- 2 大和の支配体制
- 3 天理市の状況
- 二、三昧田
- 三、旧大和
- 四、大和の風色
- 五、念仏
- 六、寺子屋
- 七、入嫁
- 八、庄屋敷村
- 九、彗星
- 十、足達照之丞
- 十一、おかげ詣り
- 十二、天保の飢饉
- 十三、よなおりの世相
- 一、御誕生のころ
- 幕末のころ
- 一、山伏市兵衞
- 二、そのころの秀司先生
- 三、「寧府記事」に現れた大和
- 四、針子
- 五、こかん様の大阪布教
- 六、天日染め
- 七、崩壊の世相
- 八、天誅騒ぎ
- 九、歌うたう教祖
- 十、初めの信者
- 十一、元治元年のころ
- 十二、守屋筑前
- 十三、小泉の不動院
- 十四、慶応三年
- 十五、維新へ
- 明治の初めごろ
- 一、明治初年の社会
- 二、そのころの信者(その一)
- 1 飯降伊蔵
- 2 種屋
- 3 竜田
- 4 松村さく
- 5 山本利三郎
- 三、大和の変貌
- 1 行政
- 2 名前の変わり
- 3 文明開化
- 四、そのころの教祖
- 五、宗教界の動き
- 1 新政府の施政方針と宗教政策
- 2 廃仏毀釈
- 3 キリスト教の迫害と解禁
- 4 天理市内の状況
- 5 教部省の活動とその挫折
- 6 奈良中教院
- 7 神道事務局の設置、神社と教会の分離
- 8 講社の発展と新宗教の発生
- 六、そのころの信者(その二)
- 1 増井りん
- 2 森清次郎
- 3 三軒家
- 4 泉田藤吉(入信前)
- 5 古市村(河内)
- 6 森田清蔵
- 七、西郷騒動
- 八、講社結成のころ
- 1 むし風呂
- 2 京都の道(明誠社)
- 3 天恵講
- 4 北前船
- 5 当時の講社
- 6 天輪王講社
- 九、道は伸びる
- 1 自由民権の世の中
- 2 大阪
- A 本田
- B 薩摩堀
- C 長堀川
- D 堺筋
- E 天満
- F そのころの雰囲気
- 3 兵庫
- 4 京都(斯道会)
- 5 新潟
- 6 遠州
- 7 東京
- 8 笠岡
- 9 播州・但馬
- 10 熊本
- 十、親里おぢば
- 1 おぢば帰り風景
- 2 参籠の思い出
- A 金魚のおかず
- B おぢばへとどく縄
- C 夜のお屋敷
- 3 参加者の印象
- A 朝起き十両(村田忠三郎氏談)
- B かぐら面(大竹芳松氏談)
- C 教祖の配分(宗我元吉氏談)
- D 柿の味
- E みりんの盃
- 4 警察の話
- A 蚊を払われた話
- B 丹波市警察
- C 櫟本の警察
- D さらしもののごとく
- E 奈良の警察
- 5 土地の人の話
- A ゆすりに来た男
- B 医師土屋の出国
- C 小学校
- 十一、公認の運動
- 1 梅谷四郎兵衛の苦心
- A 柴田某を頼む
- B 和光寺の件
- C 天輪王社
- 2 鴻田忠三郎の建言書
- 3 大日本天輪教会問題
- 4 天理教会設立事務所
- 5 神道本局員の視察
- 6 東京出願
- 1 梅谷四郎兵衛の苦心
- 十二、正月二十六日の思い出
- 1 斯道会
- 2 阿波真心組
- あとがき