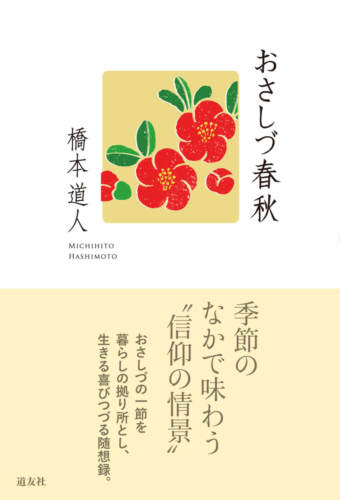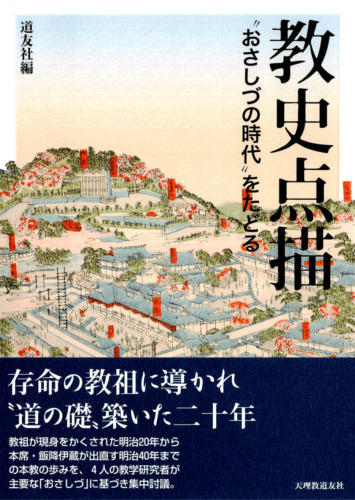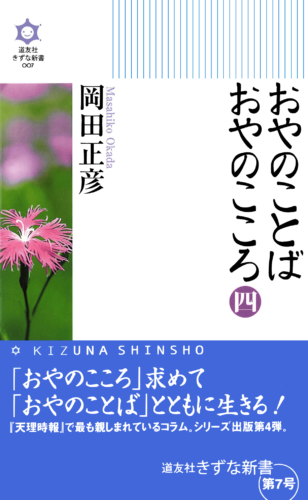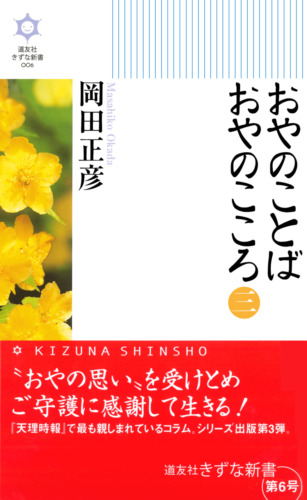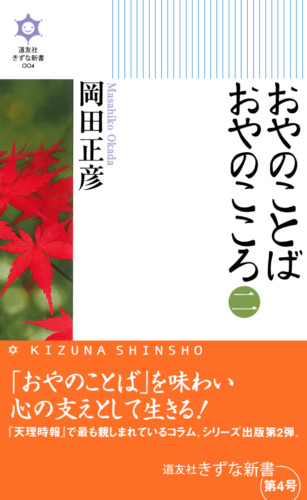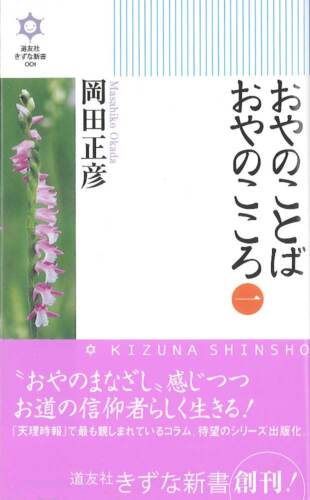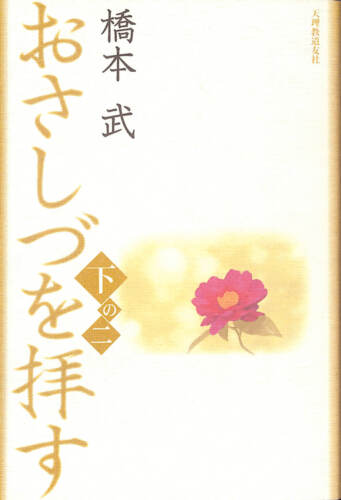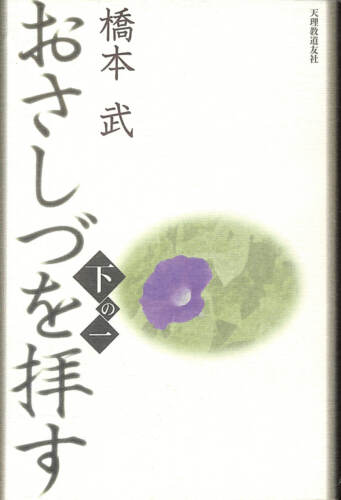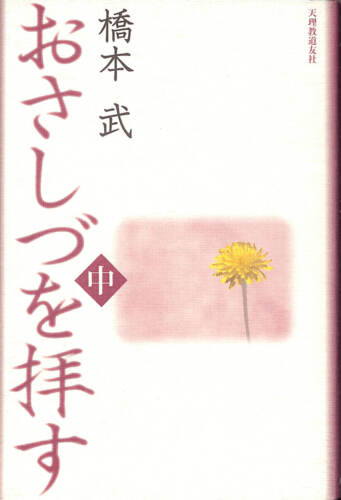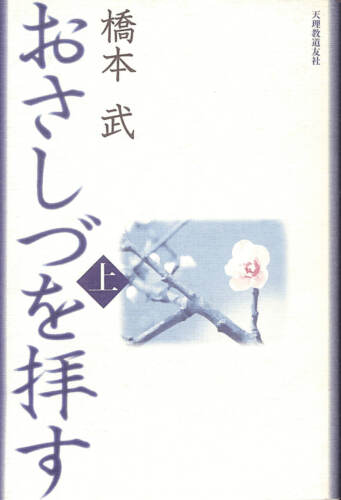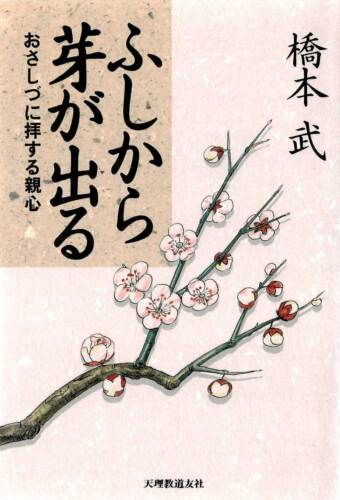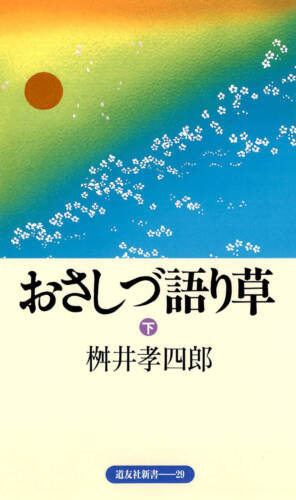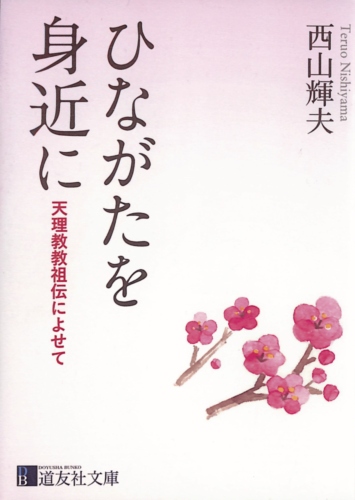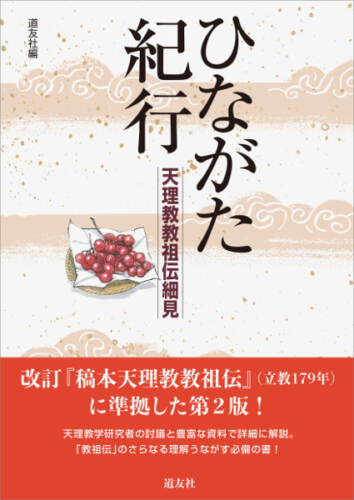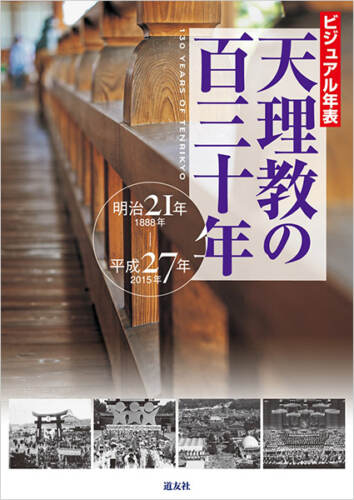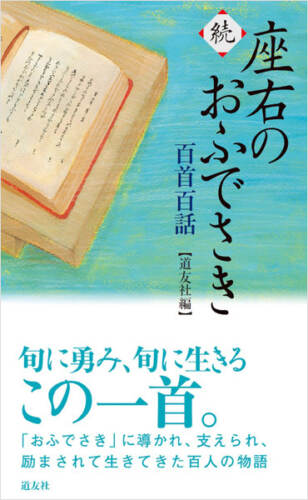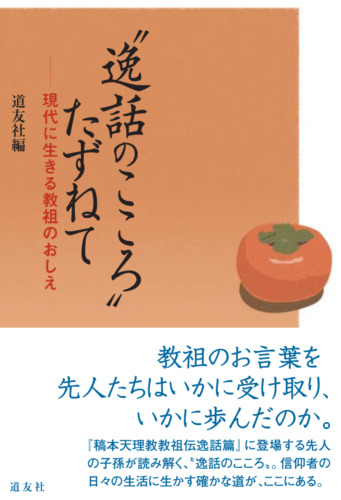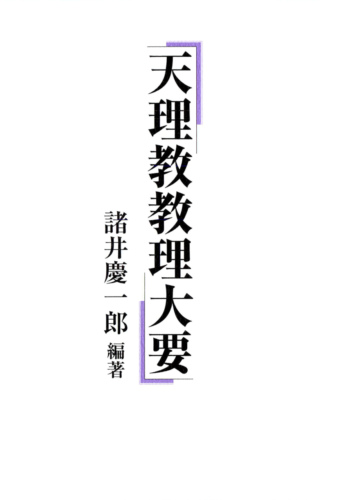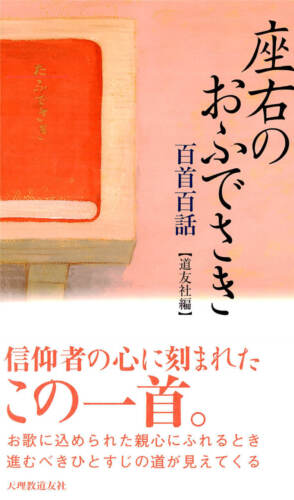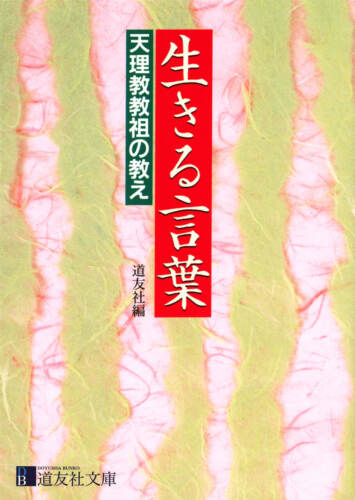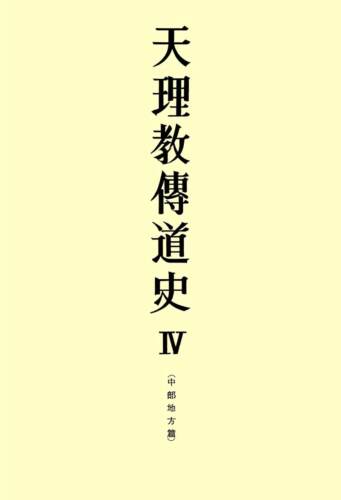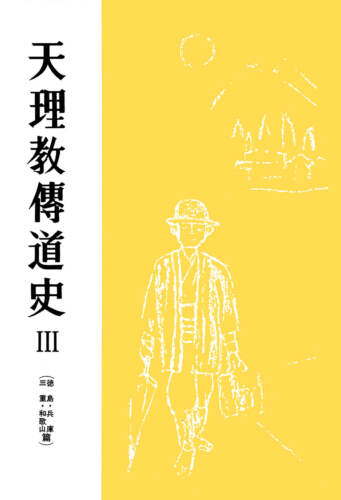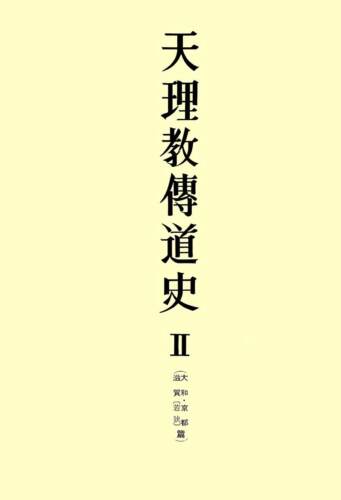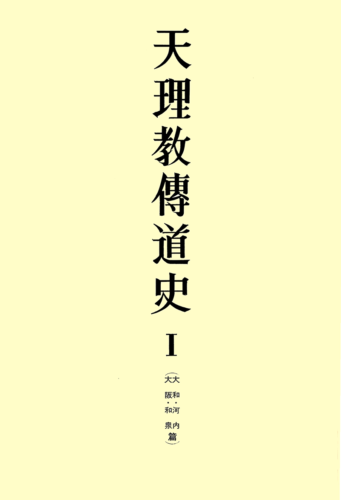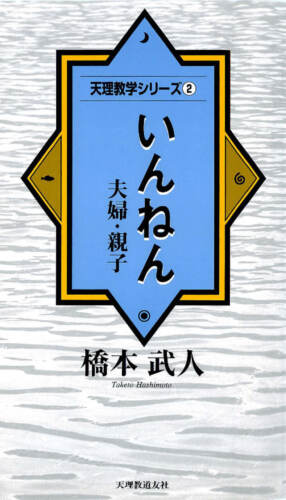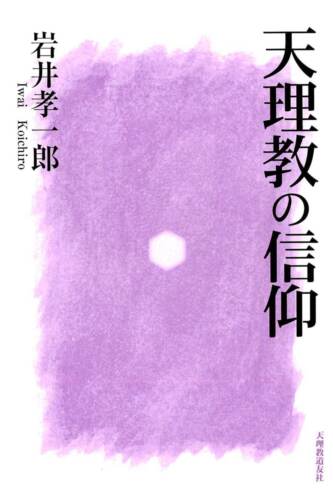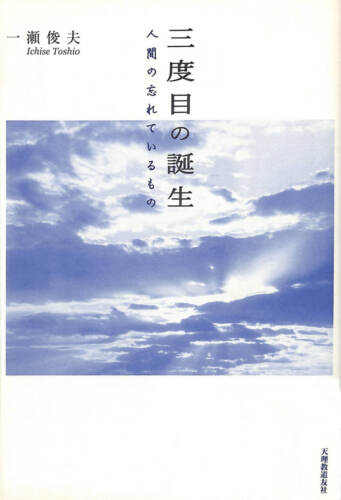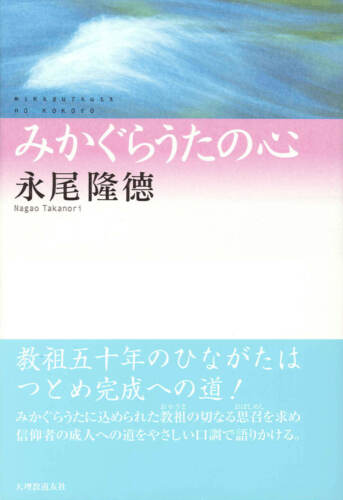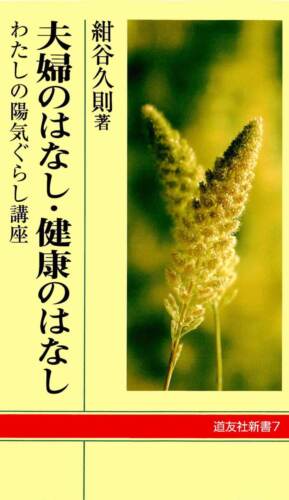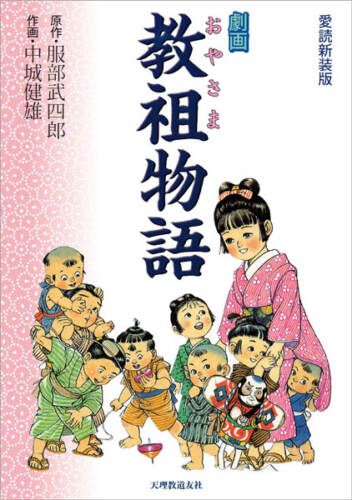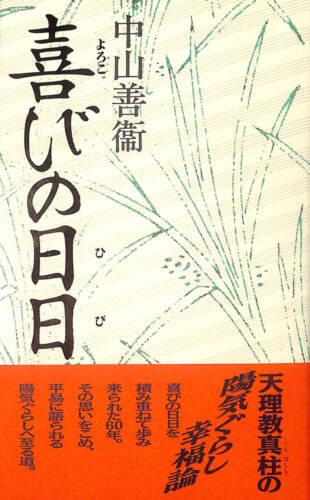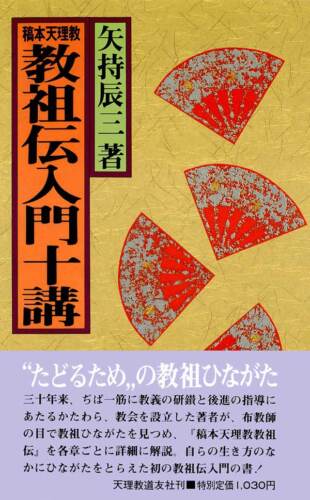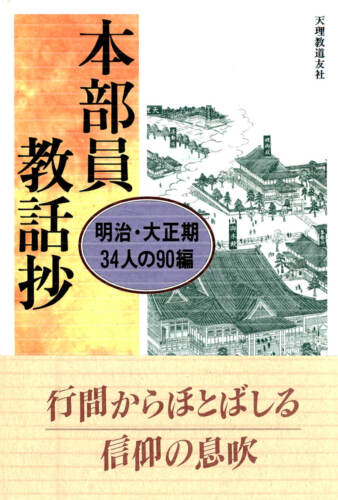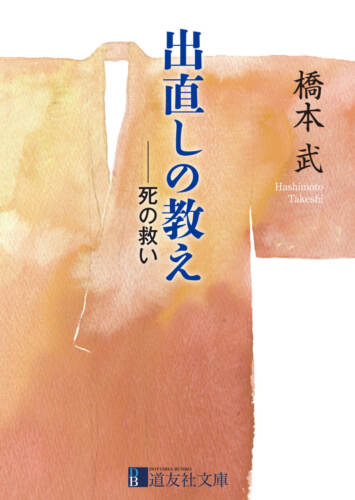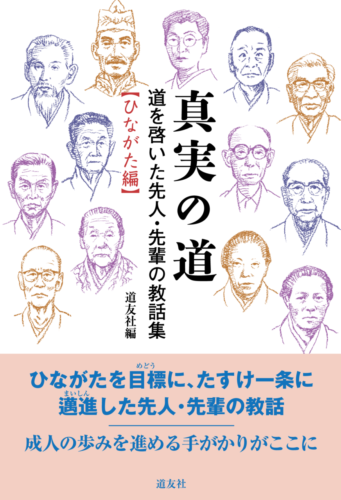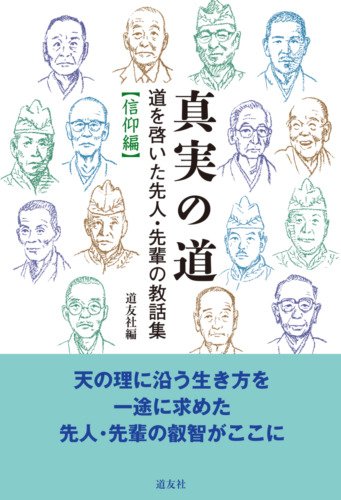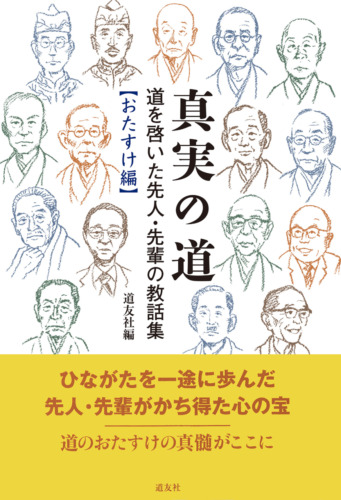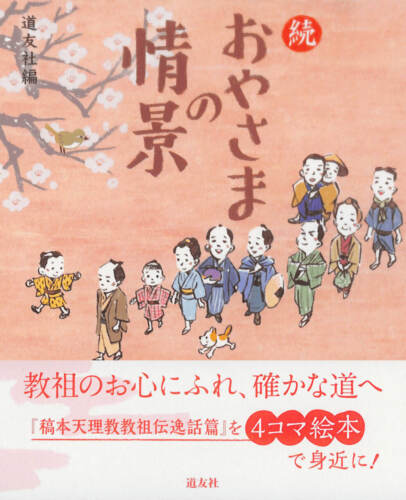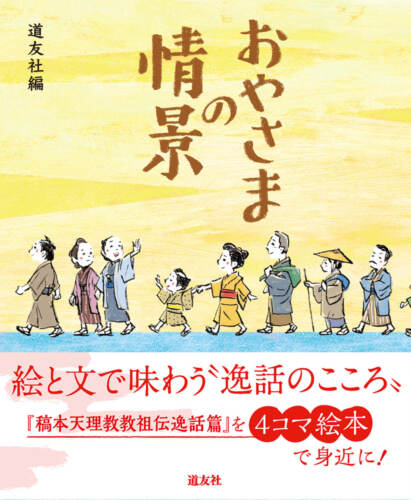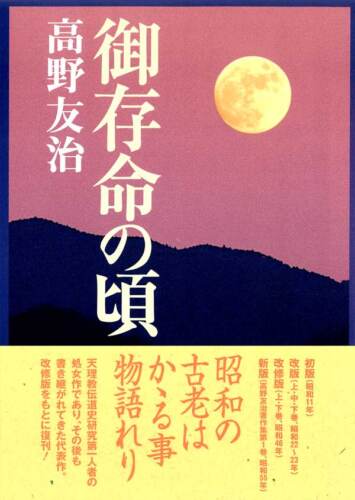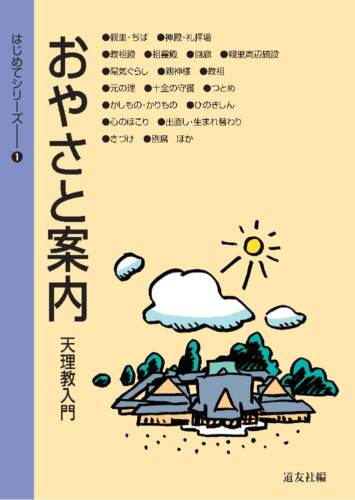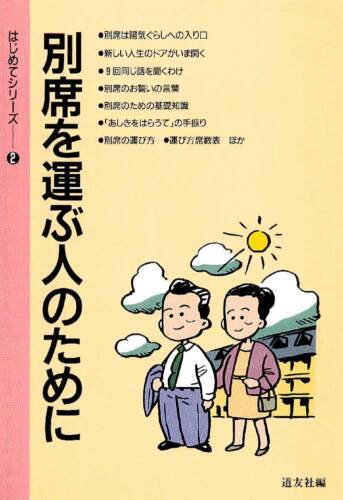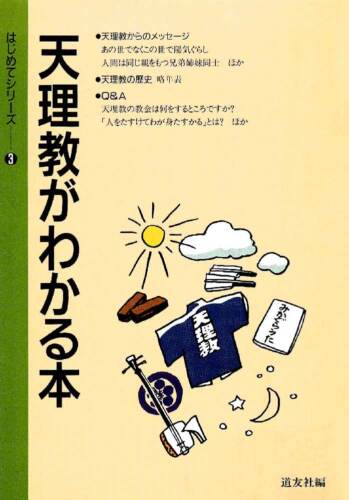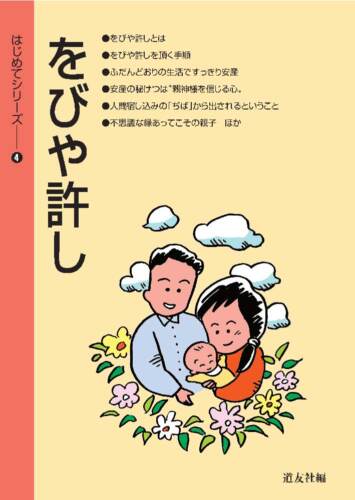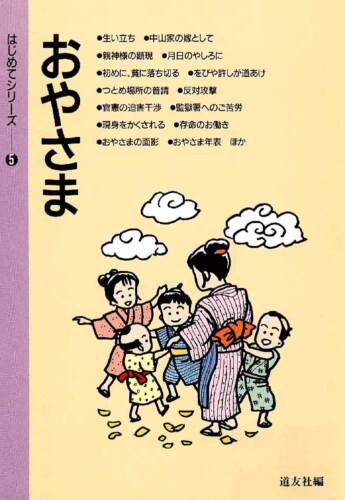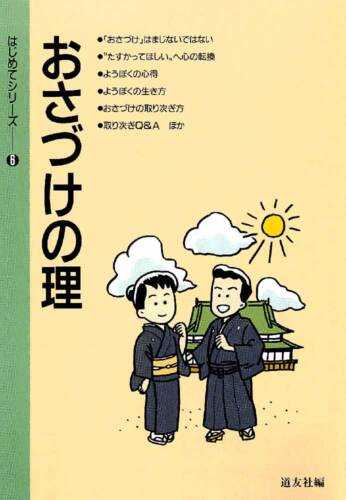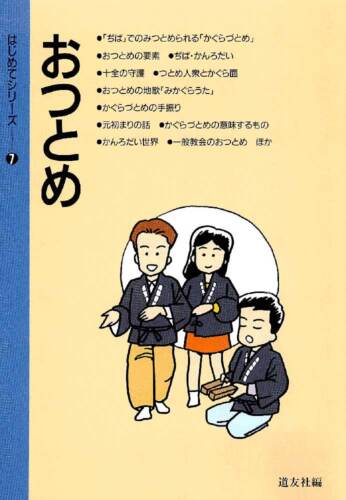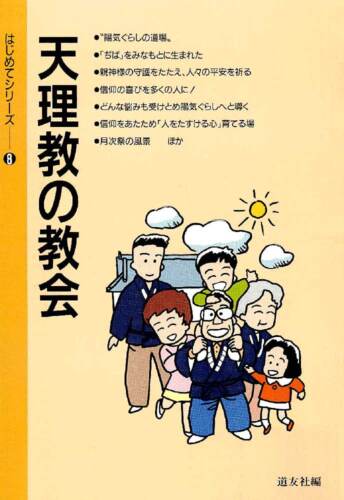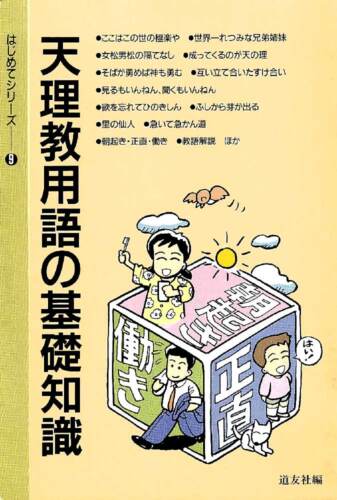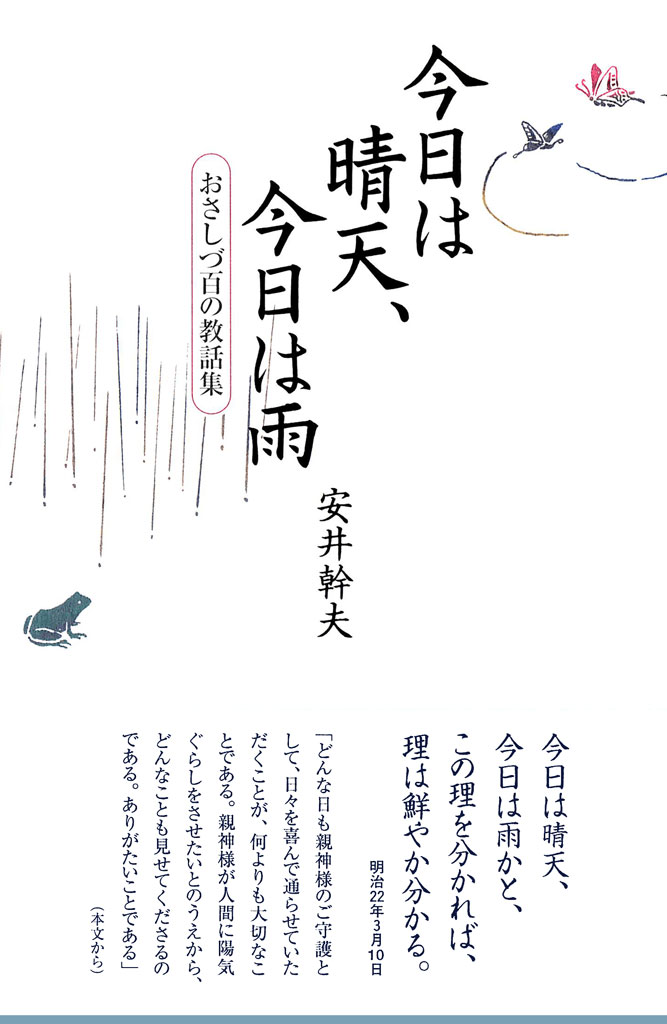
今日は晴天、今日は雨おさしづ百の教話集
著者は、『みちのとも』に5年以上にわたって「おふでさきを学習する」を執筆。また、長く天理教校等で教鞭を執ってきましたが、この本は、そういった研究者や教育者の立場からではなく、一教会長の、ようぼく・信者に向けたメッセージとして書かれたものです。おさしづの一節を引き、それをもとにして、暮らしにおけるお道(天理教)の人らしい心の置きどころ、思案の仕方などを短い教話の形でまとめています。
2005年6月 発売
紙の本の価格:¥1,100(税込)
紙の書籍を買う
月額定額で電子版が読み放題!詳細はこちら
【著者プロフィール】
- 日々・旬
- 1 自由は日々にある――日々の理を疎かにしてはならない
- 2 心だけは日々に受け取りてある――まずは形からつとめて心をつくる
- 3 心永く持って、先長く楽しみ――変化のない繰り返しの道中こそが
- 4 修理肥――日々心を掛けていくところに育つ
- 5 日々晴天唱えてくれ――心を掃除し、澄ます努力を忘れずに
- 6 日々剛気の心を以て治め――どんなことも大きな心で受けとめる
- 7 日々皆礼言わにゃならん――感謝とお礼が交わされる家庭に
- 8 日々身上壮健なら――健康で元気に暮らせるありがたさ
- 9 今日は晴天、今日は雨――どんな日もご守護と思い、喜んで通る
- 10 夕景一つの礼を言う――一日を終え「ご守護あればこそ」と
- 11 小さい/\処から始め掛け――だんだんにできてくる姿が天理
- 12 成ると成らんと理聞き分け――一切はご守護の世界と思い致して
- 13 心先々深く長く楽しみ――お互い繰り返し諭し合って通る
- 14 心だけ繋ぐなら、頼もしい――家庭の治まりが子供を育てる力に
- 15 満足は心の理――人に満足を与え、自らの満足とする
- 16 旬々の理を聞いてくれ――いまの旬に思い致し、順序を心に刻む
- 17 旬来れば花が咲く――人間・世界の根源への眼差しを
- 18 旬が来にゃ咲きはせん――真にたすかる身の処し方を教えられている
- 19 旬々の理を見て蒔けば――旬を得れば、はたらきは目に見えて明らか
- 20 旬という道という理がありて――旬は神の時間であり、神が定められる
- 道
- 21 通った中に道ある――おやさまが先頭を歩んでくださっている
- 22 今日や昨日や成りた道やない――先人の苦労あればこそ今日の結構
- 23 何も無い処より始め出来た道――全人類を一人残さずたすけ上げたい
- 24 道のため苦労艱難――魂に徳をつける道を楽しんで
- 25 草生えの中――その先には、一粒万倍の楽しみが
- 26 難儀不自由の道を通りて――元一日にみんなの心を合わせていく
- 27 難しい道――自分の心さえ少し向きを変えれば
- 28 細道が通りようて往還通り難くい――多くの人と共に歩んでいく難しさ
- 29 裏の道は誠の道――目立たぬよう、ひっそりと心を尽くす
- 30 暗がりの道が見えてあるから――知らず、分からず、みすみす、の道
- 31 満足集まって道と言う――小さな運びも大きく受け、喜びの心を表す
- 32 付け掛けた道は八方付ける――親神様の思い一つに心を寄せていく
- 33 道という理は末代の理――理を見つめて代を重ねていけば
- 34 苦労を見よ――先人の苦労の上にあぐらをかかず
- 35 無理に来いとは言わん――実行が伴わねば結構な日は見えてこない
- 36 独り成って来るは天然の理――成るよう行くよう内々治めるが肝心
- 37 勇む事に悪い事は無い――何がなんでも勇むという心の向きをもつ
- 38 楽しみの道――日々積み重ねた理が年限とともに光る
- 39 元一つの事情から始め掛ける――教会は何のためにあるのか
- 40 道の上の世界――その理の成ってくる元を心に含む
- 神の守護
- 41 大難小難救けたる――どんなことが起きても、まずお礼を
- 42 成程という理治まれば――何をもって“なるほど”と思うか
- 43 与える与えられんの理がある――ご守護を頂くには、それなりの真実がいる
- 44 御供というは大変の理――いらぬ心を使わぬよう守っていただく
- 45 教祖の言葉は天の言葉――親神様が入り込んで伝えられた教え
- 46 結構の事情は分かれども――「水を飲めば水の味がする」真実に目覚める
- 47 成っても成らいでも――親神様の思いを心において運びきる
- 48 見れば見るだけ、聞けば聞くだけ――心明るく弾ませ、嬉しい楽しい気持ちで
- 49 身の内かりもの――身体はかりものと思案しながら生きる
- 50 息一筋が蝶や花――生かされている真実を考え方の基盤に
- 51 誠の話に誠の理を添える――少しの実行の積み重ねがたすかりの種に
- 52 善い事すれば善い理が回る――「理は見えねど、皆帳面に付けてある」
- 53 明日日の事は分かろうまい――人間の知恵には限界がある
- 54 心配や難儀や苦労、神が始めるか――銘々の先案じが難儀のもとに
- 55 一粒万倍という楽しみ――与えの八分で慎みをもって暮らす
- 56 神一条の理――日々守護に心寄せるところに培われる
- 57 夜昼の理が分からにゃ――昼の理には案じることも危なきもない
- 58 こうという理が立てば――わが身可愛い心を、まず横においておく
- 59 種というは――年限がかかるほど立派なものができる
- 60 水という理が無くば固まらん――水と火のはたらきを得るならばこそ
- 身上・事情
- 61 身上に障りて諭しに出た――病気や事情のときこそ信仰が光る
- 62 身上痛めてなりと――病もまた、楽しみの種である
- 63 身上に不足あれば――身体が自分のものでないことに気づく
- 64 聞き捨てでは何にもならん――たすけたい思いに喜びをもって応える
- 65 腰掛けて休んで居るようなもの――「身上の障りの時は悠っくり気を持ちて」
- 66 そらと言うや駆け付く――どんな中も親神様を信じて通れば
- 67 身上に迫り来れば――一つの理を立てれば、みな治まる
- 68 人間の力で通れるか――どんな事情も親神様の理を頂いてこそ
- 69 元々掛かりの心になって――善きは残し、悪しきは捨てて再出発を
- 70 こうと言えばこうになる――度重なる事情でも気長く心を込めて
- 71 いんねんの理を聞き分け――末代尽くし運ぶ理によっていんねん切る
- 72 成らん事をせいと言うやない――成ってくることから心振り返り、成人の糧に
- 73 嬉しい働けば神は守る――どんな中も心を親神様に繋ぐ誠真実を
- 74 悪を善で治め――親の心と同じ地平に立てば悪が悪でなくなる
- 75 何も不自由無いから――大きな心で成人の道へ一歩を踏み出す
- 76 いんねんとさんげ――生涯にわたるいんねん自覚とさんげを
- 77 他人を寄せて兄弟一つの理――道の御用は兄弟の中の兄弟という理で
- 78 早く救からにゃならん――互いに諭し合い治め合いを
- 79 たすけ一条で救ける救かる――真実込めて一生懸命に願い勤める
- 80 教祖事情――容易ならぬ理を聞き分けていく
- にをいがけ・おたすけ
- 81 どんな者も皆寄り来る――おのずと人が寄る匂いがする人に
- 82 いつ/\までのにをい――神様の御用をつとめる中に身につく
- 83 天より付き添うて居る――どんな相手でも、ひるむことは一つもない
- 84 一人の精神の事情あれば――一国中に教えを広めることも難しくない
- 85 待って居るから一つの理も伝わる――親神様が「ここまで」と待っていてくださる
- 86 論は一寸も要らん――誠と実をもって伝えていく道
- 87 日々という、言葉一つという――日々の心遣いが言葉に表れてくる
- 88 聞かさにゃならん――人間は等しく老いも若きも可愛い子供
- 89 十分話の理を聞かし――相手を説得しようと無理してはならない
- 90 修理肥を出すは元にある――神様の話を伝えて、たすかっていただく
- 91 元は散らぬ――人間・世界の元を具現化した「つとめ」
- 92 たすけ一条は天然自然の道――まず、人さまにたすかっていただきたい
- 93 たすけ何故無い――安穏と暮らす者には珍しいたすけはない
- 94 大き深き理聞き分け――おやさまのお心をわが心としてたんのう
- 95 心に掛かる事ありては――安心という心をもってもらうのがおたすけ
- 96 席をして順序運べば――「人をたすける心」治め、おさづけを取り次ぐ
- 97 医者の手余りを救けるが台――聞いて実行するところにたすかる
- 98 国の土産、国の宝――“宝の持ち腐れ”にせず取り次ぐ
- 99 子供可愛から――成るようにすればよいとの神様の親心
- 100 実を見て、こうのう渡す――人さまにたすかっていただくための尊い理
- おさしづについて
- おさしづ割書一覧
- あとがき